|
★誕生......
― 親ならば誰しも我が子が元気に産まれてくることを信じていると思う。
もちろん私もそうだった。
妊娠経過も順調でお兄ちゃんを出産した病院での検診で先生からも「お兄ちゃんくらいまで大きくなって産まれそうだね」と言われていた。妊娠35週の妊婦検診で【羊水過多】と診断され、臍帯が赤ちゃんの頭より下にあったことで、帝王切開にした方が良いかもしれないと言われたが次の週に臍帯の位置も戻り、結局自然に出産がはじまるのを待つことになった。【羊水過多】についてネットや本で調べ、胎児に何らかの異常があり得ることも知ったが、不安を抱きつつも、絶対に大丈夫!元気に産まれてくる!と自分に言い聞かせるように毎日を過ごしていた。
★出産
2005年 1月 20日 午前1時に破水し、急いで病院へ向かった。
お兄ちゃんの時にも破水からはじまったので慌てることはなかったが、羊水過多のこともあり、早く病院でみてもらわないと臍帯が巻き付いたりしていたら赤ちゃんが苦しくなるかもしれないと心配だった。二人目ということもあり、破水してからすぐに陣痛がはじまっていた。そして、午前8時ちょうど 千雪が元気な産声を聞かせてくれた。分娩台の上で、医師から多指症であることが告げられた。もちろんその時にはびっくりしたけれど、元気に産まれてくれたことが何よりも嬉しい。そう思っていた。
きれいに体を拭いてもらった千雪が私の横にやってきた。
二人きりで約1時間くらい過ごしていたと思う。
その間に千雪は顔では泣いているのに小さな小さな声だった。
「何か元気がない・・・」そう思いはじめていた。
看護婦さんにも聞いた。
「一人目が男の子だからそう感じるんだよ。元気な赤ちゃんよ!」
そう言われたが、私のなかの不安は消えなかった。
次の日おっぱいをあげてみたけれど、吸い付く力も弱々しくて全く飲めていなかった。その時には少しずつ上手に飲める様になってくるんだって思いたかった。ほ乳瓶のミルクは、やっと飲めている。そう感じた。
2生日目、本当はその日から母子同室で過ごすはずだった。
朝、医師から千雪にチアノーゼが出ていること、別の病院へ搬送して診てもらうことを告げられた。すーっと頭のなかが真っ白になって、何も考えることが出来なくなった私がいた。搬送される前に千雪を抱っこしながら、次から次へと涙があふれ出た。そして無力な自分に腹が立ち、一緒について行けないことが、もどかしくてたまらなった。
千雪がいなくなった病院で、搾乳をはじめた。
3時間おきに新生児室まで搾乳ビンを取りに行き、冷凍バックに入れてナースステーションの冷凍庫まで持って行っていた。赤ちゃんを抱っこしておっぱいをあげているお母さんたちを目にすること、まわりの部屋から聞こえてくる元気な赤ちゃんの泣き声、すべてが辛かった。この空間に一人でいることで何かに押しつぶされてしまいそうな時間を過ごしていた。
病院から外出許可をもらい、冷凍した母乳を持って千雪のいる病院へ面会に行った。千雪は、保育器のなかでたくさんの管をつけていた。その姿に愕然としてしまった。私の心のなかに深刻な状態だと思いたくない気持ちがあったから・・・実際にその姿を見るまで、心臓に障害があることが嘘であって欲しいと思っていたから。アラームの鳴り響くNICUのなかで千雪は、小さなからだでがんばっていた。心臓疾患については説明を受けたが、とても複雑な心疾患であるのでもう少し詳しく検査をする、心臓手術を行う為に別の病院のベットが空き次第に転院することを告げられた。
私の入院先へ戻り、医師に申し出て予定よりも早く退院させてもらえる様にした。退院までの間、助産師さんが部屋に来てくれて、たくさん話を聞いてくれた。壊れてしまいそうな私の心の声を聞いてもらえることで、どれだけ気持ちが落ち着いたかしれない。日ごとにおっぱいの張りも増してきて、搾乳も助産婦さんに助けてもらった。その時お世話になった助産師さんには、本当に感謝している
★ 転院してから
転院して検査をした結果、次々と病名が増えていた。
心臓疾患があまりにも多かったので、念のためにと行った染色体異常の検査。その結果が出たのは予定していた手術の数日前のことだった。告知前夜、私の携帯電話が鳴った。担当医からだった。「面会時間以外でお話しておきたい事があります。何時に来ることができますか?」と。私は染色体異常の検査結果が出る頃だと知っていたので、もしかして・・・・
と考えていた。
―― そして翌日、私の悪い予感が現実になった。
★ 告知
「千雪ちゃんの染色体異常の検査結果が出ました。私たちも予想していない結果でした。」
と言われ、18トリソミーモザイクであることが告げられた。
はじめて耳にした『18トリソミー』の医師の説明は
◇ 90%以上は1年以内に死亡
◇ 心奇形があっても手術をすることがない
◇ 予後不良である
虫の形の様なものがはっている染色体の検査結果の紙を見ながら、これは何かの間違いじゃないか?何で悪い予感ばかりが現実になるのか?そんなことばかりが頭の中をグルグルまわり続けていた。その時、現実を受け入れることはもちろん出来なかった。告知を受けてから、心臓疾患以外に18トリソミーのことをネットでも調べたが、明るい情報がやはり少なく、いつ何が起きてもおかしくないのだと改めて感じた。NICUの面会時には「どうか明日も面会出来ますように。今日が最後ではありませんように!」そう祈りながら過ごす不安な毎日だった。
染色体異常があることで手術に伴う危険性、合併症のリスクが高くなることも含め今後の治療について、手術をする場合としない場合のメリット・デメリットを告げられ、手術を予定通りに行うか否かの判断は、私たち夫婦に委ねられた。
ゆっくり考えていいと時間をもらったものの私たちの答えは決まっていた。
手術をしない=退院は出来ない=病院で一生を過ごすということ
― 私たちは、その選択をしなかった。
少しでも可能性があるのならば血の繋がった我が子の生きる力を信じたい。やってあげられることはすべてやってあげたい。そして家族揃って家で過ごしたい。リスクの高い手術をすることに対して迷いが全くなかったとは言えない。言葉には出来ないほどの不安がもちろんあった。
手術をしてもらいたいと医師に伝え、千雪に報告した。
『がんばろうね、がんばっておうちに絶対帰ろうね』って。
★ 手術〜退院

18トリソミーについて 〜千雪の場合〜 で記したように心疾患が多数であり、
当初は合計3回の手術の予定であった。動脈管は、胎児期の血流路であり、生後肺呼吸がはじまり肺へ血液が流れてくると動脈管は役割を終えて通常自然閉鎖する。
千雪の場合は、手術前にこの血管が閉じてしまうと下半身への血流に悪影響を及ぼす。その為、動脈管開存を維持する為の内科治療としてプロスタグランディンを投与していた。
このころの千雪の主な症状は次の通りであった。
□ 肺うっ血による呼吸障害
□ チアノーゼ
□ 心不全
1回目の手術は、動脈管に頼らずに下半身の血液を循環させ、肺と体の血流のバランスをとる為の姑息術であった。肺動脈を縛ることによって肺への血流が増えすぎない様に血流を制限する→肺動脈バンディング術。大動脈の縮窄部に千雪自身の大動脈弓部の枝分かれしている3本目の左鎖骨下動脈(左手に流れる血管)を使用して縮窄部を修復する→サブクラビアンフラップ術が行われた。
手術前日、医師からとても分かり易い説明を受けた。
この手術自体は、心臓手術のなかでは難しいものではないということだった。
でも我が子が心臓の手術をするのだ。
その不安は言葉に出来ないほどであった私たちにとって、医師からの「スタッフ全員一丸となって、千雪ちゃんの為に全力を尽くします。」その言葉がどれだけ心強かったことか。
手術当日、午前8時過ぎから行われる手術の前に面会をすることが出来た。しっかり抱きしめて「ちいちゃん、みんなで待っているからね。」って言った。
― 手術の間は何度も何度も時計ばかりを見て過ごしていた。
千雪は、がんばっている!と信じていても、この時間は・・・・たまらない。手術は、予定していたよりもずいぶん早く、約3時間ほどで終了した。執刀医からの「思いのほか順調に進んで、心臓も落ち着いた状態を保っています。」
その言葉で全身の力が抜けていった。
この時の涙は、千雪が産まれた瞬間以来の嬉し涙だった。
この頃から、私自身が泣いてばかりいても事態が変わる訳じゃない!千雪だってこんなにがんばっているんだから!ってやっと思える様になってきていた。手術室〜ICUへ移る千雪の姿を、少しだけ見ることが出来た。その後、夕方までモニターに映る千雪を穴が開いてしまいそうなくらい見ていた。担当医から「今日は、もう帰っていいですよ。」そう言われても後ろ髪を引かれて、なかなか帰路につけなかった。翌日の面会の時間が待ち遠しくてたまらなかった。急変の電話が鳴ることがありませんように。そう祈りながら朝になっていた。
いつもの面会以上に念入りに手を洗い、千雪に会いに行った。
思っていたより、ずっとずっと元気そうにしていた。
本当によくがんばったね。小さな体で手術を乗り越えた千雪。
この子はきっと生きる力を持っている!
そう確信した。
この日から少しずつ点滴も外れはじめ、顔色も見違えるほど良くなった。
手術前には、経口摂取はごくわずかであったが術後は飲む量にムラがあるものの、全量経口摂取となった。
その後、一般病棟での付き添い入院を経て、術後約1ヶ月での退院となった。
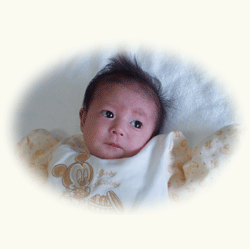
14, Mar, 2005
|
|
|