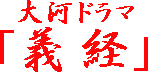
ストーリー
| 2005年12月4日放送 第四十八回「北の王者の死」 文治3年(1187年)。 都を発った義経(滝沢秀明)主従は、年を越えたこの日、ついに平泉に着いた。 藤原秀衡(高橋英樹)は「何もかも全て飲み込んで引き受ける」と義経に告げ、義経主従を暖かく迎え入れる。 義経は秀衡に亡くなった継信(宮内敦士)と忠信(海東健)の遺髪を差し出し、2人を生きて平泉に連れて戻れなかったことを詫びる。 継信と忠信の父である佐藤元治(大出俊)は、討死は覚悟の上と義経に言葉をかける。 義経に命じられた弁慶(松平健)は、腰越で忠信が彫った仏像を差し出す。 義経は弁慶たちが仏像の顔が継信に似ていると言っていると告げ、秀衡は仏像を見て頷く。 義経から継信と忠信が役に立ったと聞いた元治は、親としてこの上ない喜びと告げる。 忠衡(ユキリョウイチ)に案内され、以前住んでいた館に入る義経主従。 館には吉次(市川左團次)が都から送った荷物が届いており、そこには清盛(渡哲也)の屏風もあった。 忠衡に屏風のことを問われた義経は、描かれているのは自分たちが目指す新しき国だと答える。 義経と2人で酒を酌み交わす秀衡は、忠衡から聞いた屏風について尋ねる。 義経は屏風には清盛が福原に託した夢の都が描かれている、穏やかな町並みと異国の船の光景はいつの世にもあるべき姿に思えると答える。 秀衡は頷き、そのあたりは頼朝(中井貴一)と隔たりがあったと告げる。 義経は鎌倉には自分が望む国の形はなかった、鎌倉にあったのは規律に縛られた姿だった、平泉にこそ夢の都があるのではと話す。 秀衡に平泉を夢の都にするためになすべきことを問われ、異国との貿易を更に盛んにして富を得る、それによって領民が豊かに暮らせると答える義経。 それを聞いた秀衡は、器が大きくなったと義経を褒め、平泉で鎌倉とは違う新しき国を目指すようにと告げる。 こうして、義経主従の平泉での日々が始まった。 義経は義久(長谷川朝晴)を従えて弓の稽古をし、弁慶は読経、次郎(うじきつよし)と喜三太(伊藤淳史)は腰越で憶えた籠を作り、村人から食料をもらって戻った三郎(南原清隆)は、籠が村人に重宝されていると告げる。 義経の行き先が平泉の秀衡の元だと見た頼朝は、秀衡に義経を引き渡すようにという院宣を法皇(平幹二朗)に請うた。 京では、法皇、知康(草刈正雄)、丹後局(夏木マリ)が話し合っていた。 知康は、頼朝は義経と秀衡が1つになるのを怖れていると話し、丹後局は義経と秀衡を自分たちに引き寄せつつ、頼朝の機嫌を損なわないようにするようにと進言する。 思案する法皇。 義経引き渡しの院宣を携えた法皇の使者一行が、鎌倉に立ち寄った。 頼朝は使者に、鎌倉の雑色を1人一行に加えてほしいと申し出る。 理由を問われた頼朝は、一行を護るためと答える。 義経の館を、弁慶に戻った吉次が訪れる。 吉次は義経と弁慶に、静(石原さとみ)が鎌倉から都に戻ったと報告する。 静が鶴岡八幡宮の落慶祝いで舞い、義経を恋慕う唄を唄ったと話す吉次。 義経に静について聞かれた吉次は、静が鎌倉にて子を産んだと告げ、義経と弁慶は驚く。 子について問われた吉次は、生まれたのは姫で静と共に都にいると嘘を答える。 堪えきれず泣いてしまう吉次を見て真実を察した義経は、吉次に今までの礼を告げる。 堂で仏像に手を合わせる義経に声をかける弁慶。 義経は弁慶に、吉次は気遣って生まれたのは姫と答えたが、多分生まれたのは男児で、すでにこの世にはいない筈と告げる。 1ヵ月後、鎌倉に戻った雑色は、義経は間違いなく平泉にいると頼朝に報告する。 それを聞いた頼朝は、無理難題を突きつけて秀衡がどのように動くか見ると告げる。 今まで朝廷に献上していた貢物を、これからは一旦鎌倉に届けるようにとの頼朝の要求があったという報告を受ける秀衡。 国衡(長嶋一茂)と忠衡は、それを受ければ藤原家は鎌倉の臣下になったも同じと反対するが、泰衡(渡辺いっけい)は断われば攻め入る口実を与えるのではと心配する。 秀衡は、頼朝の要求は自分たちを試しているようだ、今回は頼朝の望み通りにすると悠然と言い放つ。 夜、秀衡と2人になった義経は、自分のことで秀衡が無理をしているのではと告げるが、秀衡が要らぬ心配と答える。 秀衡は三代続いた藤原の国を護るためならば、自分たちの意地と誇りさえ失わなければ、鎌倉より格下でもどうということはないと告げる。 義経のことは口実、源氏と自分たちには古来から、近くは秀衡の祖父の藤原清衡と源義家の頃からの宿怨がある、その頃の源氏の無念を頼朝が晴らそうとすれば、刃が藤原家に向けられるは必定と話す秀衡。 義経は自分が平泉に来たことで口実を与えてしまったと詫びるが、秀衡は義経が来なくても頼朝は口実を用意した筈、自分たちからは攻めないが、敵が白河の関を越えて攻め入ったら容赦なく討つ、義経は自分の子の1人と思い奥州藤原の全てをかけて戦うと言い切る。 秀衡が鎌倉の要求を受け入れたと聞いた政子(財前直見)と時政(小林稔侍)は、さすがの秀衡も頼朝に恐れをなしたと喜ぶ。 しかし、頼朝は時政たちに秀衡から返事と共に送られた砂金等の土産を見せ、この品々の向こうに笑っている秀衡の顔が見えると話す。 品々は秀衡の揺ぎ無い自信の表れと気付く政子に、今は奥州には迂闊には手を出せないがいつかはと告げる頼朝。 その年の秋、義経は弁慶たちと共に藤原家の宴に出席していた。 秀衡は宴の席で、今と同じ姿の100年後の奥州の夢を見たと話し、藤原家四代目を泰衡と定めると一同に言い渡す。 しかし、秀衡は今後のことを話す途中、突然その場に倒れてしまう。 泰衡はこのまま秀衡が回復しなかった時のことを心配し、自分には藤原家を導く自信はないと国衡と忠衡に弱音を吐く。 国衡と忠衡は泰衡の力になると告げ、泰衡は手をついて2人に協力を頼む。 それから1ヶ月半ほどが経った文治3年10月29日。 義経の元に、急ぎ伽羅の御所に来るようにと泰衡からの使いが訪れる。 泰衡たちに見守られて床に就いている秀衡の前に現れる義経。 秀衡は、泰衡、国衡、忠衡の3人は力を合わせ義経を将と仰いで義経の下知に従うこと、鎌倉の兵を白河の関より北側には決して入れてはならない、自分亡き後の藤原家の仕置きは泰衡を中心に重臣たちが執り行うこと、自分の死は出来る限り伏せるようにと言い渡す。 そして、義経に「九郎殿、何卒よしなに」と告げると、静かに息を引き取った。 祖父清衡から三代、財力と武力を誇り、京に引けを取らない都を奥州・平泉に築き上げた秀衡は、この日66歳の生涯を閉じた。 平泉の異変は瞬く間に諸方に広がり、もはや隠し通せないこととなった泰衡は、年が明けた文治4年正月、ついに秀衡の喪を内外に発した。 秀衡の死を知った頼朝は、藤原家四代目に義経を差し出させる院宣を、法皇に下されるよう奏上すると告げる。 一方、平泉では泰衡が義経に、亡き秀衡の遺言を守って自分たち兄弟は義経を将と仰ぐ、心配されるなと告げる。 泰衡からの返事の書状を受け取った頼朝は、平泉には義経はいないと書いてきた泰衡のことを、秀衡には遠く及ばない器量の人物だと話す。 時政に理由を問われ、義経を渡さぬと言い切る相手は手強いが、いないと逃げる相手なら突付けば必ず崩れると答える頼朝。 この後間を置かず泰衡を追い込むという頼朝の言葉に、頷く政子。 義経を頼朝に差し出すようにという法皇からの度重なる院宣に、泰衡の不安は次第に膨らみ始めていた。 泰衡に呼ばれた義経は、頼朝が諸国御家人を鎌倉に参集させ、その軍勢はすでに出陣し、行き先はおそらく奥州という報告を受ける。 国衡は予て申し合わせたように、義経を要として鎌倉勢を迎え撃つと告げる。 院宣も無しに鎌倉勢と戦うことを躊躇する泰衡に、藤原家の意地を貫くことが大事と話す国衡。 意見を求められた義経は、鎌倉勢を迎え撃ち何としても防がねばならない、自分は恩を受けた藤原家のために戦う覚悟と答え、国衡と忠衡は義経に従うと告げる。 義経は弁慶に、兄と戦をすることに躊躇いはない、自分の腹は決まっていると告げる。 |
| 2005年12月11日放送 最終回「新しき国へ」 文治5年(1189年)。 義経(滝沢秀明)の元に鎌倉勢が白河の関を打ち破ったとの報せが入り、義経は弁慶(松平健)たちに藤原家のために鎌倉と戦うと告げる。 鎌倉を出た頼朝(中井貴一)の軍勢は、すでに藤原家の領内に陣を敷いていた。 頼朝は和田義盛(高杉亘)率いる軍勢に、今後は白河の関に留まり動かないように命じる。 景時(中尾彬)も、義経が相手ではどのような目に合うかと心配する。 頼朝は広元(松尾貴史)に、泰衡(渡辺いっけい)に義経を差し出さなければ大軍を持って攻め入るとの文を、間を置かず続けて送るよう命じる。 泰衡の元には頼朝からの文が幾度も届き、それは、義経を出さなければ今にも平泉を取り囲むと思わせるほどの激しさだった。 国衡(長嶋一茂)と忠衡(ユキリョウイチ)は、泰衡に軍勢を率いて鎌倉勢を押し出す決断を迫る。 鎌倉勢に対する心構えを問われた義経は、泰衡は平泉を守り、国衡と忠衡は陸を白河の関に打って出、自分は船で海から攻める、白河の関の兵を打ち破った後はそのまま鎌倉を目指し、同じく陸と海から攻め入ると答える。 泰衡はそのようにうまくいくのかと躊躇うが、忠衡にもしや義経を鎌倉に差し出す気ではと言われて激怒、その場を立ち去る。 法皇(平幹二朗)の元には、頼朝から幾度も義経追討の院宣を願い出る文が来ていた。 何度も願い出ることを不審に思う丹後局(夏木マリ)に、知康(草刈正雄)は頼朝が法皇が義経を盾にして鎌倉に対することを怖れているためと答え、突っぱねれば恐れを知らない所業に出るかもしれないと告げる。 法皇は、頼朝の本当の狙いは義経や藤原家ではなく、自分かもしれないと呟く。 その後も泰衡の元には、脅しとも取れる頼朝からの文が届き、泰衡は混乱の極みに達していた。 弁慶、三郎(南原清隆)、次郎(うじきつよし)、喜三太(伊藤淳史)は、戦に向けての甲冑や兵糧、船や馬の準備を済ませたと義経に報告する。 そこへ義久(長谷川朝晴)が現れ、うつぼ(上戸彩)が来たと報せる。 うつぼは、自分は吉次(市川左團次)の名代として来た、静(石原さとみ)は都で母の磯禅師(床嶋佳子)と共に息災に暮らしていると告げる。 うつぼから静の「生きてさえいれば必ず会える」という言伝を聞いた義経は、うつぼに夕餉の支度を頼む。 夕餉の支度をするうつぼを手伝う喜三太は、うつぼに思いを打ち明けようとするが上手く伝わらない。 その夜、義経主従とうつぼは、酒を飲み唄を歌って踊り、賑やかに過ごした。 うつぼが着いたこの夜の賑わいは、義経主従が平泉に辿り着いて初めてのことであった。 しかし、その賑わいがいつまでも続くことはなかった。 鎌倉。 頼朝の前に現れた政子(財前直見)は、何故奥州に対して動かないのかと頼朝に詰め寄る。 政子は、藤原家さえ倒せば義経の命運も尽きるのに頼朝はそれを躊躇っている、頼朝は義経が自分の命運を悟り自害することを望んでいるのではと告げる。 「やはり頼朝様も情のお人でございますな」という政子の言葉に、「さすがに政子、よくぞ申した」と言い立ち去る頼朝。 頼朝からの最期の申し渡しともいえる文が、泰衡の元に届いた。 それには、例え院宣がなくても兵を差し向けると書かれていた。 泰衡は家臣の河辺太郎(坂西良太)を呼ぶと、密かに兵を整えるよう命じる。 泰衡が戦支度を始めたことを知った国衡と忠衡は戦の相手などを問うが、泰衡は院宣がなくても兵を送ると言う頼朝の恐ろしさを話し、藤原の家を守るのも四代目の務め、頼朝に藤原家の安堵を頼む為には義経を討たなければと告げる。 忠衡は賛同できないとその場を去り、国衡は泰衡の義経に味方すれば兄弟でも容赦しないという言葉に沈黙する。 ある朝、義経館を突然訪れた国衡は義経に、自分は平泉を去り母の生まれた所に行くと告げる。 国衡は自分と共に行き、義経主従安穏と過ごすことを勧めるが、義経は藤原家の為に戦うと断る。 国衡は去り際に「敵は何も鎌倉のみと限らん」と告げ、義経主従はその言葉の意味に気付く。 義経は弁慶たちに火急に備えるよう命じる。 火急のことは、それから幾日もしないこの日の起こった。 泰衡に呼ばれて御所を訪れた忠衡は、泰衡の家臣によって暗殺される。 戦支度で待つ義経と弁慶に、伽羅の御所に兵が集まっていると報せる三郎たち。 義経は事ここに至ったと告げ、泰衡の決断を恨むな、しかし自分たちの新しき国への試練と思い泰衡軍と戦うと弁慶たちに命じる。 そこへうつぼが現れ、戦はいけない、早く逃げるように告げる。 義経と弁慶はうつぼに、自分たちは武士、敵に背を向ける戦法はない、例え逃げても頼朝は自分の首を取るまで諦めないと諭す。 三郎はこれまでの戦の総仕上げと告げ、次郎たちは今までの合戦を笑顔で話す。 うつぼは笑顔で話す義経主従をおかしいと評すが、三郎は自分は盗賊時代に義経に会わなければどこかで果てていたかもしれない、次郎は自分はしがない船乗りで終わったかもしれないと話す。 喜三太は何か成し遂げたようだと言い、義久は満ち足りた気分、悔いはないと告げる。 弁慶は悔いはある、それは新しき国を造ることと話し、三郎たちは同意する。 義経は喜三太に脇差を授け、この機に武士の名を授けると言うが、喜三太は義経の家来になった時の喜三太のままでいたいと答える。 その時、忠衡の家来の関戸弥平(秋間登)が現れ、忠衡が泰衡によって討たれたこと、忠衡の館も泰衡の軍勢に襲われたと報告する。 弥平は、軍勢が義経館に向かっているので逃げるよう注進し、自分は門前で敵を防ぐと告げてその場を去る。 義経はうつぼに去るよう告げるが、うつぼは拒否する。 「皆、死ぬ気だね」といううつぼの言葉に、自分たちは主従なので共に逝く、共に死んでも生まれ変わって再び義経の元に従う、そういう絆で結ばれていると答える弁慶と次郎。 義経はうつぼに、「都に戻り自分たちの有様を伝えてくれ、そして、静に自分たちの新しき国ができた時は必ず呼び寄せる、それまで息災にとの言伝を」と頼む。 頷き去ろうとするうつぼを弁慶が呼び止め、喜三太の気持ちを告げようとする。 うつぼは喜三太の気持ちは解っていたと答え、都で待っていると喜三太に告げる。 義経は「またいずれ会おう」と告げ、うつぼは去って行く。 義経は弁慶たちに、今度の戦が最期と思い存分に戦おうと告げ、今まで付き従ってくれた礼を言う。 「三度生まれ変わっても我らは変わらず主従ぞ」という義経の言葉に、力強く同意する弁慶たち。 義経主従は夜が明けていくのを見つめ、最期の戦いに挑む。 襲ってきた泰衡の大軍を相手に戦う義経主従。 しかし、義久が討たれて池に倒れ、そのまま絶命する。 義久に駆け寄ろうとした喜三太は背中に矢を受け倒れ、駆け寄った弁慶は喜三太を茂みに連れて行く。 喜三太は弁慶に、「第一の家来の座は弁慶に譲りたい」と告げるが、弁慶は第一の家来は喜三太だと涙ながらに答え、喜三太は弁慶の腕の中で絶命する。 義経を狙う弓に気付いた次郎は、義経を庇って矢を受ける。 次郎は血まみれになりながら敵陣に飛び込み暴れるが、何本もの敵の槍に突かれ、花畑の中に仰向けで倒れて絶命する。 あちらこちらを斬られながらも戦う三郎だが、ついに致命傷を負う。 義経と目が合った三郎は、笑顔で「殿」と呟き、カニの真似をしてそのまま倒れて絶命する。 弁慶はその場を離れるのを嫌がる義経を、無理やり連れてその場から逃げる。 持仏堂まで逃げてきた義経と弁慶。 弁慶は持仏堂の中に義経を入れ、堂の外を護る。 義経は堂の壁に、清盛(渡哲也)の屏風の幻を見る。 幻の屏風を見ながら、「清盛様も夢半ばでございましたな。なれど新しき国、夢の都はわが胸にしかとございますぞ」と呟く義経。 そこに敵の兵たちが現れ、義経は堂に入ってきた弁慶に防ぎ矢を頼む。 別れを惜しむ弁慶に、苦労をかけたと告げる義経。 弁慶は「此度はこれにてお別れ申しますが、必ずや生まれ変わり再びお目にかかりまする」と泣きながら告げる。 外へ飛び出した弁慶は、多数の矢を胸に受けるがへし折り、薙刀を振り回して敵を倒していく。 義経は小刀を抜くと首筋に当て、新しき国を思いながら一気に小刀を引く。 その瞬間、堂の屋根を馬の嘶きと共に光が突き破り、その光は天へと上り白馬に姿を変える。 それを見た弁慶の身体に、無数の矢が刺さる。 矢を受けたまま微動だにしない弁慶の前に泰衡たちが現れ、持仏堂へと入って行く。 泰衡の「九郎殿、お許しくだされ!」という叫び声が響き渡る中、立ち往生する弁慶。 鎌倉。 頼朝の前に政子と盛長(草見潤平)が現れ、義経の自害を報せる。 都にいる吉次やお徳(白石加代子)たちは、都に戻ったうつぼから義経主従の最期を聞く。 吉次とあかね(萬田久子)は義経主従が隠れ住んだ家で義経主従を偲び、吉次は「あの方のことは、わしの胸から消えることはない」と話す。 静の家を訪れたうつぼは、義経の言伝を静に伝える。 うつぼは静に、持仏堂の屋根から光が噴出し、光は束になって空へと駆け上がった、あれが義経の最期だったかもしれないと話す。 京の町を歩くうつぼは、お徳と朱雀の翁(梅津栄)と烏丸(高橋耕次郎)に出会う。 目が見えなくなっていた烏丸は、琵琶を弾いて語りそれで生活をしていた。 お徳はうつぼに、もう嘆くな、義経はきっと鞍馬にいると告げる。 それからの鎌倉の動きは、凄まじいものがあった。 攻め入った頼朝率いる鎌倉勢を前に、泰衡は平泉に火を放って逃走。 その後、泰衡はあえない最期を遂げ、奥州にその権勢を誇った藤原家は滅びた。 そして、ここに頼朝の鎌倉幕府は揺ぎ無いものとなった。 都では、法皇が3日も晴れない天気を気にしていた。 空を見ながら暗雲が立ち込めてきたという丹後局の言葉を聞いた法皇は、鎌倉から黒雲が押し寄せてきたのかもしれないと呟く。 時政(小林稔侍)と政子は盛長に頼朝の居所について尋ね、盛長は頼朝は持仏堂に篭っていると答える。 「まさか仏門に帰依するわけではあるまいな」と告げ、笑いながら去って行く時政と政子。 持仏堂の頼朝は、初めて黄瀬川で会った義経を思い出していた。 「九郎、わしを恨め」と呟き、涙を流す頼朝。 義経の思い出は、義経に係わった全ての人の胸から消えることなく、夢に見、幻を見る度に、きっと何処かで生きているに違いないと思わせた。 うつぼは1人、鞍馬に来ていた。 そして、鞍馬の山道を走る遮那王の幻を見る。 この後、義経の消息がお徳の元に届くことはなかった。(完) |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()