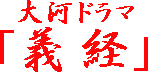
ストーリー
| 2005年11月20日放送 第四十六回「しずやしず」 鎌倉方に捕らえられて六波羅にいた静(石原さとみ)は、先行きの見えない不安を抱えて日々を送っていた。 義経(滝沢秀明)を始め弁慶(松平健)たちは、静を奪い返すための計画を練っていた。 喜三太(伊藤淳史)は、静が六波羅のどの屋敷にいるか探る役目を願い出る。 屋敷で働く者の中に自分の幼馴染がいるかもしれないと言う喜三太に、義経は朱雀の翁(梅津栄)に手を借りるよう命じる。 次郎(うじきつよし)は、静の母の磯禅師(床嶋佳子)も共に平泉に連れて行くことを進言する。 そこへあかね(萬田久子)が現れ、六波羅に静を鎌倉に送る動きがあることを報せる。 三郎(南原清隆)はそれでは自分たちの企てが無駄になると驚き、義経は急ぎ事の真偽を確かめるよう命じる。 三郎と喜三太はお徳(白石加代子)の家に向かう。 お徳と烏丸(高橋耕次郎)から、六波羅に足代の手輿が運び込まれ、輿を引く者も集められているので近々鎌倉にとの情報を聞く三郎と喜三太。 戻って義経に報告した三郎は、屋敷の中を襲うより鎌倉に向かう道中を襲う方が容易く、自分たちにとって好都合と告げる。 粟田口から近江へ向かう道中に襲い、辺りに馬を潜め静を奪い返したら琵琶湖へ向かい、そこから船で今津へ向かうと計画を練る義経主従。 その時、あかねが磯禅師を連れて訪れる。 義経は磯禅師に静を窮地に追いやったことを詫び、静を奪い返した後は共に平泉に向かい、いつの日か新しき国を作り皆で穏やかな日々を送りたいと話す。 弁慶たちは磯禅師に共に行くことを勧めるが、磯禅師は静奪還を思い留まるよう願い出る。 静は義経主従や吉次(市川左團次)たちに災いが及ばないように何も言わなかったはず、義経主従を逃がすために身代わりになった静の気持ちを汲んで欲しいと訴える磯禅師。 静を鎌倉に渡して自分たちだけ逃れることはできないと告げる義経に、磯禅師はその言葉だけで十分と答える。 3日後。 山伏の姿となった義経主従と、荷物の用意をする吉次とあかねとうつぼ(上戸彩)。 そこへお徳が現れ、比叡山延暦寺からもらった書状を弁慶に渡す。 その時、烏丸が六波羅から輿が出立すると報せに飛び込んでくる。 吉次はくれぐれも静奪還はしないよう念を押し、義経も輿を見送るのみと答える。 お徳は、共に無事でいればいつか必ず巡り会うこともあると告げる。 別れに涙するうつぼに声をかける喜三太。 出立する義経主従の無事を願い頭を下げる吉次、あかね、お徳、烏丸、うつぼ。 鎌倉に向かう輿を、都の人々に紛れながら見送る山伏姿の義経主従。 思ったより警護の兵が少ないと義経に報告する次郎と喜三太と義久(長谷川朝晴)。 三郎は山科の手前で襲えると告げ、弁慶は義経に決断を促す。 そこに朱雀の翁が現れ、輿の中は空だと告げる。 義経を誘き出す罠と義経主従が気付いた次の瞬間、1人の男が突然現れて輿の列に斬り込む。 その男が行方不明だった忠信(海東健)と気付く義経主従。 1人で兵と戦う忠信だが、義経主従の目の前で兵に斬られて倒れる。 朱雀の翁は止めを刺そうとした兵に、この先で義経主従が待ち伏せしていると告げて兵を去らせる。 朱雀の翁の手下によってその場から運ばれる忠信。 横たわる忠信に声をかける義経主従。 忠信は義経に静を護れなかったことを詫び、役目をしくじった自分を叱って欲しいと告げる。 義経は、1人で事を起こそうとして無謀だと涙ながらに忠信を叱る。 三郎の「我ら今日都を出て平泉に向かうぞ」という言葉に、微笑む忠信。 平泉にこそ新しき国の基があると告げ、忠信は息を引き取る。 兄の継信(宮内敦士)と共に平泉から義経につき従って来た忠信は、故郷を遠く離れた都で果てたのだった。 そして、その夜、義経主従は京の都に別れを告げた。 実は、この時すでに、静は密かに都から鎌倉に送り届けられていた。 鎌倉に連れて来られて以来、度重なる詮議にも一切答えない静に、この日頼朝(中井貴一)が直々に会うことになった。 頼朝、政子(財前直見)、時政(小林稔侍)らに対峙する静。 頼朝は詮議に答えない理由を尋ね、静は義経や義経を匿った人々に災いが及ばないようにすることが恩情に報いる道と答える。 静は頼朝に、義経を討つ理由を尋ねる。 「義経様を戦のみに駆り出されたのでございましょうか?義経様の評判への妬みでしょう?憎しみでしょうよ?」という静の言葉に、「弟ゆえじゃ」と答える頼朝。 静は身籠っていると頼朝に告げる政子。 驚いた頼朝は、政子に出産に付き添って生まれる子を確かめるよう命じる。 「女子なら良し、男子なら・・・良いな」という頼朝の言葉に頷く政子。 義経主従は追捕の兵から身を隠すために、道無き道を進んでいた。 義経たちが隠れている小屋に物見に出ていた喜三太と義久が戻り、近くの山里にも兵がいると報告する。 越前に入れば船で越後に渡れると話す次郎。 三郎は山伏姿なら兵に怪しまれることはないのではと問うが、弁慶は都に近いため自分たちを見知った者がいるかもしれないと答える。 義経も何としても人目は避けたいと告げる。 ある時は留まり、ある時は遠回りとその行程は遅々として進まず、季節は夏となっても、未だに近江と越前の国境辺りを彷徨っていた。 鎌倉では、静が義経の子を無事に出産する。 生まれた子は男児との報告を侍女から受ける政子。 朝になり目を覚ました静は、傍らに赤子がいないことに気付き、赤子を必死に探す。 そこに現れた政子に赤子のことを尋ねる静。 赤子は自分たちが引き取ると答える政子に、静は会わせて欲しいと必死に訴える。 政子の態度で赤子が殺されたことを察した静は、怒りと絶望で泣き叫ぶ。 頼朝を囲み、時政、景時(中尾彬)、和田義盛(高杉亘)が、義経の行方について話し合っていた。 広元(松尾貴史)と善信(五代高之)は、鶴岡八幡宮の堂の落慶祝いが迫っているが、その祝賀の余興に都で名高い白拍子の静に舞を奉納させてはどうかという声があると告げる。 景時も静の舞を見たいという御家人が多いと話し、裁断を求められた頼朝は思案する。 その夜、静の元を政子が訪れ、鶴岡八幡宮での舞の奉納を持ちかける。 静は受けると答えるが、政子は万一粗相があれば祝い事には不吉と告げる。 静はそれより舞うための支度である装束、太鼓などの鳴り物、それを奏でる腕に憶えの方々、鎌倉でそれらを用意できるのかと尋ねる。 政子は望みのままに揃えてみせると答える。 半月後。 義経主従は、山中で追捕の兵に囲まれていた。 襲い掛かる兵たちに応戦する義経主従。 その頃、鶴岡八幡宮では、静による舞の奉納が始まろうとしていた。 頼朝、政子、時政たち多くの御家人の前で、静は謡い舞う。 『吉野山峯の白雪踏み分けて入りにし人のあとぞ恋しき』 謀反人の義経を恋い慕う唄に、頼朝を始め御家人たちは驚く。 『しずやしずしずのおだまき繰り返し昔を今になす由もがな』 舞い終えた静に、政子は立ち上がり「見事じゃ」と声をかける。 「命を張って己の想いを敵の只中で披瀝した心意気、見事というほかありませぬ。思いのほか見上げた女子でありました」という政子の言葉に、沈黙する時政たち。 政子は頼朝に、赤子の命と引き換えに静に褒美を取らせて都に戻すことを進言し、頼朝も頷く。 義経主従は、ようやく越前の手前まで来ていた。 しかし、義経主従の行く手には、更なる厳しい茨の道が待ち受けていたのだった。 |
| 2005年11月27日放送 第四十七回「安宅の関」 厳しい冬も間近、追捕の目を掻い潜りながらの義経(滝沢秀明)主従の歩みは滞り、今、ようやく加賀国を目前としていた。 郎党と共に休憩をする義経に、加賀国に入ったら船を用意すると告げる次郎(うじきつよし)。 鎌倉では、頼朝(中井貴一)を中心として政子(財前直見)、時政(小林稔侍)、景時(中尾彬)、義盛(高杉亘)、広元(松尾貴史)が、義経の行方について話し合っていた。 広元は義経の行き先は奥州以外に無いと告げ、頼朝も同意する。 景時は藤原家と義経が結び付くことを案じ、義盛も平泉に着く前に義経を捕らえなければと話す。 義経一行は恐らく北陸路を下り、加賀、越後、そして奥州へ向かっているのではという景時の言葉に、思案する頼朝。 一方、義経主従は加賀国に入っていた。 休憩する義経たちの元に、船を調達に行った次郎が戻って来る。 どこの泊まりにも兵が警護していて近寄れない、船を入手するのは無理と報告する次郎。 弁慶(松平健)は義経に、このまま陸路を行くしかないと話す。 そこへ物見に出た三郎(南原清隆)が戻り、この先の木こりの者に話しかけて小屋を一晩使う許可をもらったと告げる。 喜ぶ義経主従。 小屋で暖を取り、雪で濡れた衣類を乾かす義経主従。 義経は静(石原さとみ)からもらった笛の袋を乾かし、弁慶は1本の巻物を取り出して濡れなくて済んだと喜ぶ。 義久(長谷川朝晴)に巻物について問われた弁慶は、巻物に描かれた不動明王の絵は自分が書いたもので、長年持ち歩いていたと答える。 義経と初めて五条大橋で会った時から義経の家来になると決めていたが、義経にはなかなか会えずに悶々とした日々に、気を静めるために描いたものだと話す弁慶。 そこへ、三郎が小屋の持ち主の木こりの藤太(小杉幸彦)を連れて戻る。 弁慶は藤太に羽黒山へ向かう道を尋ね、藤太はここからなら安宅の関に出る方が良いと答える。 関について問われた藤太は、安宅の関は元々あった関だが、義経の詮議がある為に関守の富樫泰家(石橋蓮司)は柵を作り変え、護りも堅固になったようだと話す。 別の道を尋ねる弁慶に、東の山伝いに行けるがこれからの時期に山道は厳しい、他は夏が来るまで無いと答える藤太。 食事ができたら運ばせると告げて藤太が去った後、義経主従は険しい山道と安宅の関のどちらを行くか悩む。 そこへ、藤太の妻のもよ(小池栄子)が食事を持って現れる。 子供を背負ったもよは義経を見て驚き、義経ももよが木曾義仲(小澤征悦)の側室の巴だと気付く。 弁慶から安宅の関の関守について問われた巴は、富樫は仏心に厚く周りの寺々に良く寄進をしているらしいと答える。 巴は富樫のことは良く解らない、武士としては頼りないと言う人もあれば切れ者だと言う人もいると告げ、その場を立ち去る。 巴の後を追い、1人で小屋を出る義経。 外で子をあやす巴に、「生きておられたか」と声をかける義経。 巴は今の自分の名はもよという、暫く死んだように彷徨い、近くの沢で倒れていた自分を夫の藤太が助けてくれたと告げる。 生きていて良かった、京で晒された義仲の首の前で「恨みや憎しみがかえって人を強くする」と言った義経のおかげと話す巴に、良かったと微笑む義経。 去り際、「諦めぬことじゃ、さすれば道はありましょう」と巴は義経に告げる。 小屋に戻った義経は、弁慶たちの様子がいつもと違うことに気付く。 弁慶たちは、先程の母子を見ていたら里心が湧いてしまったと答える。 次郎は義経に、奥州で新しい国ができた時には、駿河にいる仲違いしている兄を呼んでも良いかと尋ねる。 新しい国では異国との交易もある筈、自分と兄で船を操り、義経の役に立ちたいと話す次郎。 三郎は新しい国で妻を娶り息子を何人も作る、そして、父の墓を建てその前で父から習った弓を息子たちに教えると話す。 義久が自分は丹波から妹のまごめ(高野志穂)を呼ぶと話すと、次郎は三郎に妻を娶るならまごめだと言い、三郎は義久に「兄上、何卒宜しゅう」と頭を下げる。 次郎にからかわれた三郎が、弁慶に鎌倉から千鳥(中島知子)と杢助(水島涼太)を呼べと告げると、弁慶は元よりそのつもりと答える。 喜三太(伊藤淳史)は、自分はうつぼ(上戸彩)を呼んで子を作ると告げる。 さっきの母子のように子が泣いたらあやし、笑ったら共に笑う暮らしをという喜三太の言葉を、穏やかな笑顔で聞く義経 義経はそれぞれ何かを背負っている、男と女が出会い夫婦となり父と母になる、そのような有様が愛しくいじらしく思えると話す。 喜三太は必ず静を新しき国に招く日が来ると言い、弁慶はその為にも何としてもここを切り抜けて平泉へと告げる。 義経は明日は安宅の関を通る、仏心の厚い富樫に望みをかけようと告げ、弁慶たちは頷く。 そして、翌日。 弁慶を先達とし、安宅の関に着いた義経主従。 修行の為に比叡山から出羽・羽黒山へ向かう山伏と名乗る弁慶たちを、不在の富樫に代わりに詮議する役人の井家八郎(得丸伸二)。 延暦寺の僧の俊章からもらった書状を見せる弁慶。 書状を読んだ井家は、弁慶らに通行を許可する。 弁慶たちが立ち上がり関を通ろうとしたその時、関守の富樫が現れ、井家は弁慶らに富樫を迎えるよう命じる。 酔って現れた関守の富樫泰家に、弁慶たちについて報告する井家。 立ち去ろうとする弁慶たちを富樫は呼び止め、義経主従が山伏に身を変えているという噂もあるので些かの不審がと告げる。 井家に名乗るよう命じられ、弁慶は大和坊、三郎は伊勢坊、次郎は駿河坊、喜三太は山城坊、義久は摂津坊、義経は和泉坊と名乗る。 義経を疑いの目で見る富樫。 この時期に羽黒山に修行に行くことが解せない、羽黒山の四季の修行について問う富樫に、弁慶は羽黒山の四季の修行について語り、四季の修行に関係なく入山して荒行を重ねる覚悟と答える。 富樫はならば急ぐことはない、2、3日館に留まるよう勧める。 弁慶は自分たちは修行の傍ら、東大寺大仏殿再建の勧進を務める身と断る。 滅多に見れない勧進帳を冥土への土産に拝見したいという富樫の申し出に、弁慶たちは黙り込む。 返答しない弁慶たちに、井家は「ニセ山伏か!」と叫ぶ。 弁慶は勧進帳は見せるものではないと答えるが、富樫はならば聴かせろ、それができないのなら1人とて関を通さないと迫る。 笈の中から、小屋で義経らに見せた不動明王が描かれている巻物を取り出す弁慶。 そして、弁慶は何も書かれていないその巻物を開き、勧進帳として朗々と読み上げる。 勧進帳聴聞の上は速やかに通してもらいたいと告げる弁慶に、黙り込む富樫。 弁慶たちがその場を足早に去ろうとしたその時、富樫は立ち上がって「和泉坊、その方待て!」と叫ぶ。 義経に駆け寄った富樫は、「この和泉坊の懐に不審あり」と告げ、義経が懐に差しているのは笛ではと問う。 弁慶は義経の懐から笛を取り出し、富樫は山伏が何故笛を携えているのかと義経に厳しく問う。 「和泉坊、そなた真に山伏か?」と問い、構える富樫と兵たち。 弁慶は咄嗟に義経を地面に叩きつけ、金剛杖で義経を打つ。 義経は寺に来た人の笛を盗んだと侘び、弁慶は義経を何度も強く杖で打ち、静の笛を踏み潰す。 義経に駆け寄ろうとする喜三太と義久を、必死に抑える三郎と次郎。 皆に迷惑をかけたことを謝れと義経の体を地面に押さえつけ、再び金剛杖で激しく義経を打ち続ける弁慶。 涙を流し義経を打つ弁慶と、痛みに耐える義経。 富樫は弁慶を制止し、「笛の経緯、得心致した」と告げる。 富樫は義経に、痛みで眠れなかった時は飲むようにと酒を渡し、「もう二度と盗みは致すなよ」と告げる。 そして、富樫は弁慶たちに先を急ぐよう命じ、弁慶たちはその場から立ち去る。 弁慶たちを見送り、「九郎殿」と呟き頭を下げる富樫。 山道で、弁慶は義経を叩いたこと、笛を踏み潰したことを泣きながら義経に詫びる。 三郎は「弁慶、1人で苦しむな。わしはおぬしと殿の姿を見て、己が何と非力かと思うとったんじゃ」と泣きながら告げ、次郎も自分たちは心の中で手を合わせていたと声をかける。 義経の「そちの苦しみは我が苦しみじゃ。そして皆の苦しみじゃ。礼を言うぞ」という言葉に、号泣する弁慶。 義経主従、目指すは一路奥州平泉であった。 |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()