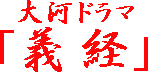
ストーリー
| 2005年7月3日放送 第二十六回「修羅の道へ」 非業の最期を遂げた木曾義仲(小澤征悦)の首が、鎌倉方に届いた。 義経(滝沢秀明)は範頼(石原良純)から、義仲の首が検非違使によって獄門にかけられることを聞かされる。 義仲への情を見せる義経に、例え同族でも頼朝(中井貴一)に仇なす者は晒し首になると知らしめるのも必要と諭す範頼。 義仲は逆賊であるという景時(中尾彬)の言葉に従う義経。 義仲の首は獄門にかけられ、都人の憎しみに晒された。 首を見に現れた義経は、義仲の首に石を投げようとする者を制し、ふと「許せぬ」と呟く1人の女に目を留める。 それは巴(小池栄子)であった。 義経に気付いた巴は義経に対して短刀を抜こうとするが、義経はそれを制し「命を無駄になさるな。恨むなら恨まれよ。憎しみや悲しみがかえって人を強くすることもある」と告げる。 巴に義高(富岡涼)のことを尋ねられた義経は、自分が何としてもと答え、巴はその場を去って行く。 義経は鞍馬へ向かった。 幼い頃から6年の年月を過ごした懐かしき鞍馬寺であった。 お堂で手を合わせる義経の背後に覚日律師(塩見三省)が現れる。 「約束を守ったな」という覚日律師の言葉に頭を下げる義経。 覚日律師は義経に、何故平家と戦うのかと問う。 義経は平家を滅ぼし源氏の世とし、争いの無い新しき国を頼朝と共に作る為と答える。 覚日律師の「何れにしても修羅の道じゃな」という言葉に、「覚悟の上」と答える義経。 平家の拠点は、都にあと一歩の一ノ谷であった。 一度は都を落ちた平家であったが、再び西国を従え源氏を凌ぐ力を盛り返していた。 知盛(阿部寛)と重衡(細川茂樹)は、時子(松坂慶子)や宗盛(鶴見辰吾)に平家の布陣を話す。 東の生田を知盛と重衡が守り、西は忠度(清盛の弟で六男)を大将に備えるという説明に、山側はどのようにと尋ねる時忠(大橋吾郎)。 知盛は一ノ谷の北側は急峻な崖の為、敵も攻めることはできないと答える。 知盛らの説明に満足そうに頷く時子。 次の日、義経は丹後局(夏木マリ)に召し出されていた。 丹後局と会話をする義経の様子を、次の間から密かに後白河法皇(平幹二朗)が見ていた。 義経が去った後、義経について話す法皇と丹後局。 法皇は義経について「人が良いというのか甘いというのか、情にほだされる者は情を欲しているともいうが」と評する。 法皇にとっては御し易いようだが、武士としての器量は解らないという丹後局の言葉に、もう少し様子を見ると答える法皇。 宿所に戻った義経を喜三太(伊藤淳史)が迎え、あかね(萬田久子)が訪ねて来ていると告げる。 郎党に笑顔で促され奥の部屋に入った義経は、あかねの隣にいる静(石原さとみ)の姿に驚く。 弁慶(松平健)、三郎(南原清隆)、次郎(うじきつよし)らにこの屋敷で静と共に暮らすよう促される義経。 静の気持ちはどうなのかという忠信(海東健)の問いに、嫌と言う筈がないと答え静に問いかける次郎。 一同が静の返事を待つ中、三郎がそっと義経を促す。 義経から「如何じゃ?」と問われた静は、母が気掛かりと答えるが、母と共に参るようにという言葉に笑顔で頷く。 静の母の磯禅師(床嶋佳子)は、静と共に義経の屋敷に行くことを断わり、静に義経の妻にはなれないと告げる。 義経の側にいたいという静の固い決心を知った磯禅師は、自分の装束を静に渡す。 鎌倉では頼朝が京からの報告の文を読んでいた。 義経が義仲の首を晒すことに異議を唱えたという報告に、義経はそういう人だと告げる政子(財前直見)。 頼朝と政子にとっては、それよりも義仲の死を義高に告げることの方が問題であった。 時政(小林稔侍)は義高に義仲の都での所業や討死したことを話す。 今まで通り大姫(野口真緒)の婿として過ごすようにと告げる時政に、「ありがたく承りましてございます」と手をついて答える義高。 義高の殊勝な振る舞いに感心したという時政の報告に、頼朝は清盛(渡哲也)と対面した時の自分を思い出していた。 知らず知らず己の本心を隠して殊勝にと心がけたと話す頼朝は、柱に隠れるように立っている大姫の姿に気付く。 大姫の「義高様はどうして泣いておられるのでしょう?」という問いに、言葉を失う頼朝、政子、時政。 義高は縁の下で1人泣いていた。 静は庭に花を植え、義経はそれを見て静に声をかける。 その時、弁慶達の怒鳴り合う声が響く。 弁慶と三郎が取っ組み合いを始め、継信(宮内敦士)と忠信が間に入って止めさせようとしていた。 そこへ義経と静が現れ、事の次第を尋ねる。 三郎が弁慶に鎌倉の千鳥(中島知子)に会いたいのではと言い出したのが発端で、次郎は三郎を庇い、喜三太は弁慶と共に「三郎はからかって楽しんでいるだけ」と怒っていた。 静は千鳥と離れて暮らす弁慶の胸の内をからかうものではないと諭し、三郎と次郎はおとなしく従う。 その様子に微笑む義経。 その夜、義経は静の笛に耳を傾けていた。 しかし、酔った弁慶達の唄に邪魔をされる。 弁慶、三郎、次郎、喜三太に加え、継信と忠信も唄って踊って楽しそうに過ごす様子を見守る義経と静。 義経は「望んでいたのはこのような日々。郎党や静と身内同士集まって、仲睦まじいこのような暮らし」と話し、静は「いつまでも続けばようございますのに」と答える。 一ノ谷。 戦を心配する時子に、一ノ谷は護るに易く、攻めるに難しい天然の要害と話す知盛。 重衡から維盛(賀集利樹)への沙汰を促された宗盛は、通盛(清盛の弟の教盛の長男)の下に就くよう言い渡す。 知盛は資盛(小泉孝太郎)に、宗盛の陣を頼むと告げる。 その時、海に船が現れたとの報告があり、敵かと心配する時子に知盛は、平家に従う阿波の水軍だと話す。 鎌倉では、頼朝、時政、義時(木村昇)、和田義盛(高杉亘)、安達盛長(草見潤平)による評定が行われていた。 平家追討の院宣は近々下ると話す頼朝は、都の範頼に三種の神器を何としても手に入れることを厳命するよう義盛に言い渡す。 三種の神器を手に入れても、ただでは法皇に返さないという頼朝の考えを聞き、頷く時政達。 京でも範頼を中心とした軍議が行われていた。 平家の兵の数は約10万に膨れ上がったという義経の報告に、源氏の兵は6万、一ノ谷に向かえば敵の術中に陥るのみと告げる景時。 景季(小栗旬)は都には平家と繋がりのある公家がいる為、源氏の兵の動きはすぐに平家に伝わると心配する。 義経は昼となく夜となく都の警護として兵を動かしておけば、出陣の兵か見分けがつかないのではと進言する。 範頼は義経に搦手を任せる。 義経は丹波路を進み、一ノ谷の北をまわって敵の背後を突くと告げる。 範頼率いる本軍は、山陽道を一ノ谷の東の生田へ進み、敵の正面に挑むことにする。 全軍布陣した上、矢合わせは2月7日早朝と決まる。 宿所に戻った義経を、静や弁慶達が迎える。 そこへ三郎と次郎が現れ、客人が訪ねて来たと義経に告げる。 お徳(白石加代子)がそろそろ戦の気配がすると言っていたと、差し入れを持って訪ねて来たうつぼ(上戸彩)であった。 うつぼは義経の傍らにいる静に気付き、義経はうつぼに静を、静にうつぼをそれぞれ紹介する。 うつぼは喜三太を睨みつけ、喜三太は気まずそうに顔を逸らす。 弁慶や佐藤兄弟も視線を逸らし、三郎と次郎はその場を取り繕くろうようにうつぼに話しかける。 しかしうつぼはそれを無視し、静の名を昔聞いたことがあると話す。 うつぼは静のことは知っていたと明るく振舞い、その場から立ち去る。 寿永3年(1184年)1月29日。 院の御所で範頼と義経は、平家追討と三種の神器の奪還を命じられる。 遂に平家追討の院宣が下されたのだった。 宿所に戻った義経は、郎党に出陣は今夜、それまでに準備を整えるよう命じる。 弁慶達はすでに、馬、物具、兵糧、一ノ谷の絵図と出陣の準備をしていた。 出陣の夜、郎党は静に礼を告げ、身支度の為にその場を離れる。 2人きりになった義経と静は、今生の別れになるかもしれないと言葉を交わす。 静は義経の前に白拍子の姿で現れ、武運を祈る舞を披露する。 戦支度で待つ郎党と共に出陣する義経。 馬で都を出立する義経主従の後を追って来たうつぼは、義経に自分が静の面倒を見ると告げる。 義経主従はついに、運命の一ノ谷へと出陣したのであった。 |
| 2005年7月10日放送 第二十七回「一の谷の奇跡」 後白河法皇(平幹二朗)により平家追討の院宣が下され、寿永三年(1184年)1月29日夜半、義経(滝沢秀明)率いる源氏の軍勢は小勢に分かれて都から出陣した。 範頼(石原良純)の本陣は山陽道を西に進んで平家方の正面を突き、義経の搦手勢は丹波路を進み、一ノ谷の北側を西へと向かい敵の背後から攻めかかる手筈であった。 法皇は知康(草刈正雄)から源氏の兵が出陣したことを報告を受ける。 平家の兵10万に対して源氏の兵6万と聞き、平家が勝てば三種の神器が戻らないと憂う法皇。 亀岡の義経の陣では、軍議が行われていた。 安田義定(真実一路)から、矢合わせは2月7日早朝卯の刻と聞く弁慶(松平健)達郎党。 一ノ谷の北側の様子を気にする義経。 船乗り時代に海から見たことがある次郎(うじきつよし)が、屏風を立てたようなそそり立つ崖だと話すと、弁慶は天然の要害だと感心する。 義経は東西の城戸口を攻めれば逃げ場はないと呟く。 一ノ谷では、宗盛(鶴見辰吾)が源氏が都を出たとの報告を受けていた。 知盛(阿部寛)は、源氏勢は2手に分かれて本軍は東の生田、搦手は西から一ノ谷を挟み撃ちにする作戦だと告げる。 矢合わせの日を問う重衡(細川茂樹)に、宗盛は清盛(渡哲也)の命日、陰陽道の悪い日などを考えて7日ではと話し、知盛も同意する。 平家の兵が迎え撃つ準備をする中、知盛は重衡に源氏勢にみすみす挟み撃ちをさせる手はない、西へ向かう三草山の麓の道を断つと話す。 鎌倉の頼朝(中井貴一)のもとには、範頼が都を出陣したとの報せが届く。 法皇に対して強く出る為に必要な三種の神器を手に入れられるかどうか、範頼と義経の戦いぶりを気にする頼朝。 本軍の範頼が生田の東に陣を敷いた翌日、搦手の義経の軍勢は三草山の近くまで進んでいた。 義経は谷の向こうに敵がいる気配を感じ、三郎(南原清隆)と次郎に物見を命じる。 物見に向かった三郎と次郎は平家の大軍を発見し驚く。 京の六条殿では、法皇が丹後局(夏木マリ)に平家に戦に負けてもらおうと話していた。 蝸牛の角を引っ込ませるようなわけにはいかないと言う丹後局に、自ら書状を平家に送ると告げる法皇。 お徳(白石加代子)の家では、うつぼ(上戸彩)が烏丸(高橋耕次郎)と共に義経のことを心配していた。 三草山近くの義経の陣に戻った三郎と次郎は、谷の向こうの山陰に7千の平家の兵が陣を敷いていたと報告する。 帰り道に迷った三郎と次郎は、出会った土地の猟師の鷲尾三郎(長谷川朝晴)と妹のまごめ(高野志穂)を、何かの役に立つかと思い陣に連れて来ていた。 鷲尾三郎は、一ノ谷の西に行く道は三草山を通る以外にないと告げる。 義経は一ノ谷を高見から見ることを希望し、一同は鵯越の先へと向かう。 京の義経の宿所にいる静(石原さとみ)のもとを、うつぼが訪れる。 うつぼは困ったことはないかと尋ね、静はうつぼの気遣いに感謝する。 鵯越にやってきた義経達は、一ノ谷に設けられた平家の陣を見下ろし感嘆する。 義経は軍議で、堅固な護りの一ノ谷の平家の軍に勝つ為に、戦の前に様々な仕掛けを講じた方が良いと話す。 景季(小栗旬)に方法を問われ、三草山の平家勢に大軍を装い夜討ちをかけると答える義経。 夜討ちの報せは一ノ谷の本陣にも伝わり、平家は更に兵を差し向けるという考えだった。 夜討ちとなれば、敵味方の区別がつかず同士討ちになると心配する義定に、義経は火矢と太鼓があればよいと告げる。 三郎とまごめ、次郎と鷲尾三郎は2手に分かれ、三草山の麓の里の人々を説得して退去させる。 その夜、義経は火矢を無人となった集落に向けて放ち、それに続いて三郎、継信(宮内敦士)、忠信(海東健)が次々と火矢を放つ。 義経軍は弁慶の指揮で、用意した鐘や太鼓を鳴り響かせ大声を上げた。 闇の中の火は更に炎を上げ、鐘や太鼓の音、鬨の声は山間に木霊して三草山の平家勢に襲い掛かった。 夜討ちに平家の兵たちは騒然として混乱し、資盛(小泉孝太郎)はやむなく退却する。 義経の軍勢が平家の陣に到着した時には、兵の姿はなく平家の赤旗が散乱していた。 義定は義経の作戦を見事と褒め、義経はこのまま西へと告げる。 資盛率いる三草山の軍勢が、夜討ちを受け退却したとの報告を聞く知盛達。 宗盛は屋島に逃げた資盛に激怒する。 急ぎ三草山に兵を差し向けることを進言する重衡に対し、知盛はそれよりも東西の城戸口を固めるよう告げる。 宗盛は頷き、急ぎ三種の神器と安徳帝(市川男寅)や時子(松坂慶子)らを船に移らせるよう命じる。 この日の昼、宗盛のもとに平家と源氏の和睦を勧める法皇の書状が届く。 書状には、源氏の返答を持って8日に使いが来るので、それまで戦をせずに待つようにと書かれていた。 和睦に応じるのかとの重衡の問いに、宗盛は和睦に応じれば平家一門が都に再び上ることもある、ここは使いを待つと答える。 知盛は重衡に、備えは怠りなくと告げる。 ところが源氏方には一切、法皇からの書状など届いてはいなかった。 法皇から何の仰せもないことが気味が悪いと言う政子(財前直見)に、頼朝は「法皇様は今何をお考えか。考えておられるのか、おられぬのか。動かれるのか、動かれぬのか」と話す。 義経は義定に軍勢を2手に分けると告げる。 義定は本隊としてこのまま西に進み、自分は精鋭70騎で一ノ谷の背後に向かうと話す義経。 突然の作戦変更に驚く義定に、義経は敵陣の様子次第で打つ手を変えるのも兵法、常のことでは形勢が変わらず、敵の不意を突いて突き崩すと告げる。 景季、弁慶、三郎達が同意し、義定も承知する。 三種の神器を奉ずることを念押しした義定は、義経主従と分かれ一ノ谷の西へと向かう。 寿永3年(1184年)2月7日卯の刻、一ノ谷の東で範頼の攻めを皮切りに合戦が始まった。 生田口の知盛の陣に、範頼軍が攻めてきたとの報告が入る。 法皇から持ちかけられた和睦の話は、相手方の源氏には何一つ知らされておらず、東西の城戸口では激しい戦いとなっていた。 知盛と重衡は急ぎ範頼軍との戦いの場へ向かう。 その時、一ノ谷の平家の陣を見下ろす急峻な崖の上に義経軍が姿を現す。 義経は鷲尾三郎にこの崖を獣が通うかと尋ね、鷲尾三郎は鹿はよく通うと答える。 義経は「我らこの坂を下りる」と告げ、弁慶達はその言葉に動じず眼下を見下ろし「おう!」 と叫ぶ。 しばしの沈黙の後、義経は腕を上げ、「方々、参る!」と叫ぶ。 その声を合図に、弁慶達は急峻な崖を一気に下って行った。 のんびりとしていた平家の兵達は、突然頭上から襲いかかってくる騎馬武者達に気付き、慌てて身支度をして迎え撃とうとするが時すでに遅く、義経軍に陣幕は裂かれ、兵はなぎ倒される。 船上にいた宗盛は義経軍の襲撃を知り、帝のいる御座舟を護りを固めるよう叫ぶ。 一ノ谷の東、生田の森では知盛と重衡が源氏勢に応戦していた。 逆落としで一ノ谷が攻められているとの報告を聞き、重衡が一ノ谷へ向かう。 義経主従達は次々と平家の兵を倒していく。 和睦の話は、法皇が平家を油断させる謀だったと気付き呆然とする宗盛。 生田の森から駆けつけた重衡は、戦う義経に向けて矢を射ようとするが、それに気付いた弁慶によって馬から落とされる。 生け捕りにしろという義経の命で、重衡を取り囲む兵。 重衡は自分を捕らえた義経が、幼い頃に遊んだ牛若(神木隆之介)と知り愕然とする。 苦戦を強いられていた東西の城戸口の源氏勢であったが、義経の逆落としの奇襲によって平家方は混乱し、船にて難を逃れるのがやっとであった。 船に逃れた知盛は宗盛と共に一ノ谷を見つめ、鵯越に兵を置かなかったことを悔やんだ。 戦い終わった義経主従のもとに範頼、景時(中尾彬)、景季が現れる。 範頼は義経の逆落としを褒め労うが、景時は三種の神器を奪い損ねたことを指摘して去って行く。 こうして一ノ谷の合戦は源氏の勝利で終わった。 都へ戻った義経主従を待っていたのは、人々の賞賛の嵐であった。 捕虜となった重衡を引き連れ、誇らしげに凱旋する義経主従を、密かに牛車から法皇と丹後局が見ていた。 意外にも戦上手だった義経を「あの者、使えるな」と丹後局に告げる法皇。 |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()