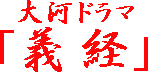
ストーリー
| 2005年7月17日放送 第二十八回「頼朝非情なり」 寿永3年2月7日一ノ谷、戦いは義経(滝沢秀明)の逆落としの奇襲が功を奏して、源氏方が勝利を収めた。 戦いに敗れた平家は三種の神器を奉じ、帝と女院と共に四国の屋島へ行宮を移した。 義経の名声は、1日にして都に轟いたのであった。 義経主従は静(石原さとみ)の待つ宿所へ戻る。 義経主従の無事を喜び、涙で迎える静に声をかける義経。 都に戻った義経だったが、ゆっくりと過ごす暇も無く戦の始末に奔走していた。 範頼(石原良純)を中心とし、生け捕りにした重衡(細川茂樹)の扱いについて義経、景時(中尾彬)、安田義定(真実一路)らの話し合いが行われた。 頼朝(中井貴一)の裁断を仰ぐべきと言う範頼に、景時は敵方の大将の首を刎ねるのは戦の定法、いちいち頼朝の裁断を仰ぐのでは戦目付としての自分の務めが果たせないと訴える。 義経は平家の重鎮である重衡の命と引き換えに、三種の神器の返還を迫ってはと提案する。 平家が三種の神器の返還を拒んだ場合は斬首にという義経の言葉に、頷く範頼。 初めは書状を送ることを渋っていた重衡だったが、ついに源氏方の意に屈して書状を書く。 屋島の平家に届けられたその書状を読んだ時子(松坂慶子)や輔子(戸田菜穂)、領子(かとうかずこ)は、重衡が生きていることに安堵するが、宗盛(鶴見辰吾)は三種の神器の返還を拒否する。 輔子や明子(夏川結衣)は重衡の命を救ってほしいと懇願するが、知盛(阿部寛)は三種の神器を返還しても、重衡の命が助かり平家の行く末に安穏がもたらされるとは限らないと告げる。 泣き崩れる輔子に知盛は、重衡の行く末に望みがあるとすれば、源氏方の軍に義経がいることだと話す。 しかし、宗盛は一ノ谷に奇襲をかけたのは義経だと一蹴し、三種の神器が帝と共にある限り、平家は官軍だと告げる。 平家方の決断は都の源氏に伝えられた。 重衡の処刑が正式に決まりかけたその時、鎌倉より頼朝の書状が届く。 書状には、重衡を鎌倉に護送するように書かれていた。 義経は範頼に護送の役目を願い出、範頼は義経に重衡護送の役目を命じる。 数日後義経主従は重衡を鎌倉に送るため都を出立した。 義経一行が駿河の国に入った頃、義経は重衡に話しかける。 義経は新しき国を作ろうとする頼朝に従い、頼朝の力になるために戦ったと告げる。 幼い頃、義経のことを弟だと思っていたと話す重衡に、自分も清盛(渡哲也)を父と思い、知盛と重衡を兄と思っていたと答える義経。 「平家に恨みがあって戦に臨めたらどれほど心易かったか」という義経の言葉に、重衡は「宿命じゃな」と答える。 その数日後、重衡を伴った義経は鎌倉に着き、頼朝と対面した。 三種の神器を取り返せなかったことを詫びる義経に、一ノ谷の働きを褒める頼朝。 そして頼朝は、都より招いた2人の文士、大江広元(松尾貴史)と善信(三善康信)(五代高之)を義経に紹介する。 頼朝は義経の重衡護送の労をねぎらい、暫く鎌倉に留まるよう命じる。 時政(小林稔侍)と政子(財前直見)に対面した義経は、2人から一ノ谷の労をねぎらわれる。 政子は義経に、義高(富岡涼)は義仲(小澤征悦)の死を知っているが大姫(野口真緒)は知らないと言い聞かせる。 政子に義高と大姫に会うよう勧められた義経は、その場を立ち去る。 時政は都での義経の評判の良さや、共に戦った者達が賞賛していると政子に告げる。 政子は人を惹きつける魅力のある義経を警戒する。 義経は大姫の館を訪れ、義高と大姫に会う。 義経との再会を喜ぶ義高と大姫。 何も知らない大姫は無邪気に、義高に義仲のことを義経に尋ねるよう勧める。 義経は意を決して、義仲からの「すまぬ」という言葉を義高に伝える。 数日後、頼朝は初めて重衡と対面した。 広元や善信らから三種の神器や南都焼討について問われた重衡は、それらに堂々と答え、「武士であるならば敵の手にかかり命を落とすことは恥ではない、自分の首を刎ねられよ」と告げる。 頼朝は重衡を命を取るには惜しいと評し、重衡を伊豆の工藤狩野介に預け、丁重にもてなすよう命じる。 その夜、漁師の杢助(水島涼太)の家に義経主従が集まり、ささやかな酒宴が行われた。 三郎(南原清隆)と次郎(うじきつよし)は、一ノ谷の合戦の話を面白おかしく杢助と千鳥(中島知子)に聞かせた。 やがて義経達は気を利かせて一斉に杢助の家を出、弁慶(松平健)は千鳥と2人きりになる。 千鳥は弁慶に、熊野に行ってみたいと話す。 理由を問う弁慶に、千鳥は熊野別当の湛増から熊野詣にくるよう誘われていると答える。 以前、杢助が嵐にあって流された熊野水軍の船乗りを助けたところ、熊野水軍の頭である湛増が未だに杢助らに礼を届けていると話す千鳥。 義経が鎌倉に留まっている間に、怖ろしい出来事の芽が密かに顔を出していた。 大姫の乳母の深井(藤田むつみ)が義高の侍女の楓(杉山佳穂)に、義仲が晒し首にされたことを大姫に話したことについて問い詰めていた。 楓は頼朝が義仲を討ったこと、その追討軍に義経がいたことも大姫に話していた。 そこに現れた大姫は、自分が何としても義高を護ると2人に告げる。 それから数日後、楓は寺で父の命日の務めをするためにという口実で、女装した義高と共に鎌倉を脱出する。 義経は継信(宮内敦士)から、義高主従が大姫の館から出奔したとの報告を聞く。 出奔を知った時政は、義高主従を見つけるために四方に兵を出し、ほどなくして義高主従は鎌倉の兵に捕らえられる。 御所へと連れて来られうなだれる義高を、無言で見つめる頼朝。 政子は頼朝に、義経が目通りを願い出ていると告げるが、頼朝は会うことを拒否する。 政子は大姫のためにも、義高の命を助けてくれるよう頼朝に頭を下げて懇願する。 盛長(草見潤平)は頼朝が会わないことを義経に伝える。 義高の処遇のことでと告げる義経だが、盛長は首を横に振る。 義経は義高への寛大なる処遇を賜るように頼朝に伝えてくれるよう、盛長に必死に訴える。 自室で一晩考えていた頼朝は盛長を呼び、「義高が首、刎ねよ」と言い渡す。 そして義高の処刑は遂行された。 弁慶が義経に、義高の斬首を報告する。 その場に泣き崩れる弁慶、三郎、次郎と言葉を失う義経。 義経は慌てて大姫の館を訪れるが、大姫は義経も頼朝と同じ、顔も見たくないと義経に向かって叫び去って行く。 呆然とする義経に、盛長が頼朝が呼んでいると告げる。 頼朝の部屋を訪れた義経は頼朝と向かい合う。 頼朝は義経に「以前、義高を亡き者にした方が良いと口にした家人を斬首にした。それほどの思いを義高には向けていたのに、逃げるというのは自分への裏切りではないか」と問う。 義高は若年故に思案の及ばないこともあるともあると答える義経に、今の義高はかつての自分達兄弟と同じだと告げる頼朝。 義経は「源氏が1つになって新しき国を作ろうとしている時に、身内同士でこんなことをしていては」と訴えるが、頼朝は「身内でなくとも結束できる。身内の情に頼りすぎて平家は脆くも崩れた。長い目で見れば、非情もまた情ということもある。新しき国は何も源氏の世ということではない。武士の国じゃ」と義経に告げる。 その言葉に衝撃を受ける義経に、自分が目指す新しき国は、自分に従う者達の国、源氏や平家など関係ない新しき武士の国だと話す頼朝。 頼朝は義経に京都守護を命じ、支度をして都に戻るよう言い渡す。 頼朝の部屋を出た義経の胸の内は、千々に乱れていた。 義経は兄の頼朝との間に、はっきりとはしないまでも微かな隔たりを感じていた。 義経主従は都へ向けて出発した。 これが頼朝との最後の対面になることなど、この時、義経は知る由もなかった。 |
| 2005年7月24日放送 第二十九回「母の遺言」 鎌倉から都に戻った義経(滝沢秀明)には、頼朝(中井貴一)の代官としての務めが待っていた。 範頼(石原良純)は頼朝の命を受け、景時(中尾彬)や土肥実平(谷本一)らと共に鎌倉に戻った。 範頼の後を任された義経は、訴訟の裁定や平家方に内通する者の取り締まりなどに追われた。 鎌倉・大倉御所。 大江広元(松尾貴史)や善信(五代高之)、時政(小林稔侍)が一ノ谷における義経の活躍に対して恩賞を与えるよう、頼朝に進言していた。 頼朝は義経の働きは認めるが、後白河法皇(平幹二朗)や朝廷が義経1人を持ち上げることを気にする。 朝廷では、法皇、丹後局(夏木マリ)、知康(草刈正雄)が鎌倉に都を作ろうとしている頼朝に対して警戒心を抱いていた。 法皇達は、頼朝が家人を国司に推挙してきたが、そこに義経の名前がないことに着目する。 頼朝と義経の兄弟の間には何かがあるのではと察し、そのことを利用することを画策する。 一条長成(蛭子能収)の屋敷を訪れた吉次(市川左團次)は、長成から常盤(稲森いずみ)が2、3日前から病に臥せっていることを聞く。 吉次から常盤のことを聞く義経。 静(石原さとみ)と吉次は義経に常盤の見舞いに行くよう勧めるが、義経は常盤と交わした「二度と一条邸を訪れない」という約束を破ることになると告げ、見舞いに行くことを断わる。 義経の気持ちを察した吉次は、薬草など病に効く物を届け、常盤の様子を逐一義経に報告すると告げる。 屋島・平家の陣。 この日、病弱を理由に都に残っていた経子(森口瑤子)が屋島を訪れた。 時子(松坂慶子)、宗盛(鶴見辰吾)、知盛(阿部寛)らに、経子は維盛(賀集利樹)が入水して果てたことを告げる。 維盛が屋島を出奔した折に付き従っていた家人の家貞(来須修二)の報告によれば、維盛は一旦紀州の国に着いたものの行く手を阻まれ、熊野の沖に船を出し海に身を沈めたのだった。 経子から維盛が屋島を出奔した理由を問われた知盛は、維盛は誰にも何も告げずに屋島を去ったと答える。 資盛(小泉孝太郎)は時子や宗盛らに、これからは維盛の代わりに自分が源氏との戦で働くと願い出る。 知盛は資盛の心意気を褒め、維盛の死を無駄にすることなく源氏を蹴散らそうと一同に告げる。 6月、かねてから頼朝より推挙されていた範頼らに国司の任官があったが、公家衆の間では何の任官もなかった義経への同情の声が俄かに広がった。 弁慶(松平健)ら郎党は、義経に何の任官も恩賞もなかったことに対して不満を噴出させていた。 三郎(南原清隆)と次郎(うじきつよし)はこれからの戦次第と弁慶らを宥め、義経もこの後の戦いが大事だと告げる。 屋島。 時子の館に領子(かとうかずこ)、明子(夏川結衣)、輔子(戸田菜穂)、能子(後藤真希)が集まり、庭の蛍を鑑賞していた。 領子は能子が産んだ子は、平家と源氏のどちらの血筋になるのかと問うが、能子は自分に流れるのは清盛(渡哲也)の血だと答える。 領子らが帰ろうとすると、時子は明子1人を呼び止める。 時子は明子に、自分が皆に告げた「頼朝の首を墓前に供えよ」という清盛の遺言が、偽りだったと打ち明ける。 時子はその後、平家一門が戦に負け続けて都を落ち、次々と一門の者を失うことになったのは、自分の偽りの遺言の災いではないかと話す。 明子は時子の遺言が偽りだったことは誰にも言わず、2人だけの胸の内に納めるようにと告げる。 一門の者達が巻き返しを計るためにも偽りの遺言は必要だった、遺言は清盛の言霊だったのだという明子の言葉に頷く時子。 7月。 都では平家と共に屋島にいる安徳帝に代わる新帝(後鳥羽天皇)が即位したが、そこに三種の神器が無いため正式な即位とは言えなかった。 そして8月6日、義経は法皇に召し出され、検非違使左衛門少尉に任命される。 頼朝の承認を得ていないことに戸惑う義経だが、丹後局や知康から義経への恩賞は頼朝への恩賞でもあるという説得をされ、ついに任官を受ける。 一条邸。 常盤は長成から、今回の義経の検非違使判官への取立てによって、頼朝と法皇との間で駆け引きが生じ、この度の任官はそういった含みがあるのではと聞かされる。 常盤は義経は真っ直ぐ育ったために人の裏表を知らないと話し、義経の将来を憂う。 義経の検非違使左衛門少尉任官の報告は、鎌倉にも届いた。 政子(財前直見)はこのままでは義経は法皇に取り込まれ、義経の甘さは鎌倉の命取りにもなり兼ねないと話す。 頼朝は「九郎、何故事が見えぬのか」と呟き、出陣した範頼に急ぎ文を送ると告げる。 8月初めに鎌倉を出陣した範頼の軍勢が都に着いたのは、8月も末のことであった。 範頼らを迎えた義経は、範頼から義経は今回の戦に加わらなくても良いとの頼朝の命を告げる。 平家追討軍から外され、愕然とする義経。 弁慶ら郎党も、これは頼朝の罰ではないかと怒りを顕にする。 それから数日後、頼朝の使いが義経の屋敷を訪れた。 使者は頼朝の沙汰として、河越重頼の息女の萌(尾野真千子)を奥方として遣わせると告げる。 三郎は静がいるのだから断わるように義経に進言するが、継信(宮内敦士)は奥方を受け入れるよう進言する。 驚く弁慶達であったが、継信は頼朝は義経に法皇の家人か頼朝の家人かを問うているのだと説明する。 頼朝は義経が法皇より検非違使判官に任じられたことを気にしていると話す継信に、忠信(海東健)は頼朝の家来ということは法皇の家来でもあるのではと反論し、義経も何故頼朝は鎌倉と朝廷を分けて考えるのかと問う。 その時、次郎が義経主従の話を聞いていた静に気付く。 静は義経に屋敷を去ると申し出る。 弁慶や喜三太(伊藤淳史)達は、真の奥方は静なのだからこのまま屋敷に留まるよう願い出、義経も静にそばにいてほしいと話す。 静は承知するが、万一障りが出た時は身を引くと告げる。 こうして数日後、頼朝から差し向けられた義経の奥方の萌が、義経の屋敷に入った。 ある夜、病の身を押して常盤が義経の屋敷を訪れた。 平家追討軍から外され、奥方を迎えさせられた義経に、常盤は思いもかけないことに翻弄された昔の自分と同じように思えると話す。 「真っ直ぐな性格な為に物事を曲げることは嫌かもしれないが、密やかな謀や企みの渦巻く中ではキレイ事だけでは生きてはいけない。くれぐれも身の処し方を誤ることの無いよう物事を見定めよ。表もそしてその裏も見極めよ。善も悪も、鎌倉も法皇様をも」と告げた常盤は、義経に見送られ去って行く。 その2日後、義経の屋敷を土御門通親の使者が訪れ、義経を月見の宴に招待する。 支度をして土御門家へ向かおうとする義経の前に弁慶が現れ、常盤が危篤だと告げる。 義経は通親に断わりの使者を出し、一条邸へと急ぐ。 しかし一足遅く、常盤は息を引き取っていた。 長成は義経に、常盤が今際の際まで義経の名を呼んでいたと告げる。 義経は横たわる常盤の遺体に、礼を述べて頭を下げる。 |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()