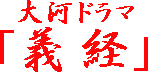
ストーリー
| 2005年8月7日放送 第三十回「忍び寄る魔の手」 頼朝(中井貴一)の命により平家追討から外れた義経(滝沢秀明)は、都の守護の務めを果たしていた。 帰館した義経は、弁慶(松平健)らと共に平家追討で兵が都から減ったために増えた夜盗について話し合っていた。 三郎(南原清隆)と次郎(うじきつよし)は義経が平家追討ではなく夜盗を相手にしていることを嘆くが、義経は戦に出向くも都の守護も大事な役目と2人を諌める。 正室として鎌倉から送られた萌(尾野真千子)が挨拶に現れるが、義経の態度は素っ気無い。 その時、外からうつぼ(上戸彩)の声が聞こえ、三郎と次郎が慌てて外へ向かう。 うつぼは宥める喜三太(伊藤淳史)や三郎、次郎に対し、義経は静(石原さとみ)がいながら何故他の女性を娶ったのかと食って掛かる。 そこへ静が姿を現し、うつぼを静の部屋に招き入れる。 静はうつぼに義経や自分の立場を話し、うつぼも納得する。 その頃、西国では長門の彦島にいる知盛(阿部寛)が山陽道で源氏方に幾度となく攻めかけ、範頼(石原良純)率いる源氏の軍勢は思うように進めずにいた。 後白河法皇(平幹二朗)と丹後局(夏木マリ)は、義経に検非違使を命じたことで義経と頼朝の間に溝ができ、義経が平家追討から外されたと、自分達の思惑通りにことが進んでいることに満足していた。 都では夜盗の群れが相変わらず我が物顔で暴れ回り、その取締りは思うに任せない状況であった。 ついに義経は、闇の世界に通じている朱雀の翁(梅津栄)に盗賊達を集めるよう頼んだ。 集まった盗賊達の前に現れた義経は、幼い頃に五足(北村有起哉)や烏丸(高橋耕次郎)達と屯していた白鷺(池田鉄洋)や赤目(飯泉征貴)に声をかけ、彼らも義経が牛と呼ばれていた少年と気付く。 義経は盗賊達に、戦で手柄を立て所領をもらった時には耕す土地を与える、それまでは都で盗みに走る者達を取り締まってほしいと話す。 義経は力で押し潰しても都から孤児や盗みは無くならない、盗賊達自らの手で無くしてほしい、力を貸してほしいと訴え、盗賊達も義経の言葉に頷く。 この後、都から少しずつ夜盗の横行が減っていった。 御所に召し出された義経は、知康(草刈正雄)から検非違使としての働きを褒められ、従五位下の位を与えると言い渡される。 しかし、義経は先ずは頼朝の許しを得たいと答え、法皇もそれを許可する。 義経からの書状を受け取った鎌倉の頼朝は思案にくれていた。 萌を正室として受け入れ、今回は位をもらうことの伺いを立ててきたということで、義経が自分の立場を忘れているわけではなさそうだと話す頼朝に、政子(財前直見)は義経に何と返事するのかと尋ねる。 頼朝は、自分に無断で法皇から賜った官位を自ら名乗る義経を、どう見たら良いかと悩む。 政子は、今回のことは鎌倉抜きにはことが進まないことを法皇や義経に解らせる良い機会、返事は出さない方が良いと進言する。 義経は法皇から召し出しを受ける。 鎌倉からの返事がまだ来ていない中での法皇からの呼び出し、しかも場所が御所でなく寺ということを心配する弁慶と継信(宮内敦士)。 義経は法皇という人を見極める良い機会かもしれないと告げる。 寺へと赴いた義経は、法皇への直答を許される。 義経と2人きりとなった法皇は、寺に呼んだ理由は先頃母を亡くした義経を慰めるためと告げ、義経はその言葉に感激する。 法皇は義経に優しい言葉をかけ、自分も義経同様に親の縁に薄い人生を送ってきたと声を潤ませて語る。 親子兄弟が争うことのない末永き安寧の日々がほしいという法皇の言葉に、同意して法皇の力になることを誓う義経。 義経の様子に満足する法皇。 それから暫くして御所に呼び出された義経は、知康から従五位下に叙せられる。 義経としても、これ以上断わり続けることは敵わないことであった。 弁慶は鎌倉の動向を気にするが、継信は義経の立場としては仕方がないと諭す。 義経はこの後の自分の働きを見てもらうより他はないと話す。 静も義経を心配し、「吉事の後には不吉が申します。何卒ご用心なされますよう」と告げる。 その頃鎌倉は、1つの大きな節目を迎えていた。 頼朝は新たに公文所(所領のことと政の細々したことを扱う)と問注所(争いごとの裁きを行う)を設け、大江広元(松尾貴史)を公文所別当に、善信(五代高之)を問注所の執事に任じる。 一方、政子は大姫(野口真緒)の様子に驚く。 義高(富岡涼)斬首後、大姫は誰とも口を聞かず、ついに食事を取らなくなり、顔色も悪く目つきも朧で、このままでは乾死(飢え死)になるという状態になっていた。 政子は頼朝に大姫の様子を伝え、義高を斬首したことが原因と詰め寄る。 大姫のもとに現れた頼朝は、横たわる大姫に義高のことを詫びるが、大姫が「義高様、私も側に参ります」と呟くのを聞き愕然とする。 頼朝は大姫の心を癒す為に、亡き義高の供養塔を建てその法要を行った。 しかし、大姫の様子が変わることはなかった。 そして、義経が従五位下の位に叙せられたという報せが鎌倉に届いた。 このところ不吉なことばかり起き、これは祟りではないかと頼朝に話す政子。 政子は頼朝に、新しい要職に北条の者や頼朝挙兵以来従ってきた者ではない都下りの者達を登用したことを責める。 頼朝は政子に、今後政に対する口出しは無用と告げる。 口出し無用と言われたと聞いた時政(小林稔侍)は、このままでは北条は脇に追いやられると不安を顕にする。 しかし政子は、今回のことで頼朝は実は人一倍情を欲している小心な人だと解ったと話す。 政子は時政に「焦られますな」と告げ、時政も頷く。 10月、義経は御所への昇殿を許された。 これほどの短い間に御所への昇殿を許されたことは、公卿衆などもさすがに驚きを隠せなかったようであった。 義経邸を平泉から戻った吉次(市川左團次)が訪れた。 藤原秀衡(高橋英樹)から託された「身辺くれぐれもご用心なされますように」という義経への言葉を伝える吉次。 用心とは何にという喜三太の問いに、義経の破格の栄達だと答える弁慶。 義経は自分の栄達は頼朝のため、必ず解ってもらえる筈と話し、弁慶達は頷く。 そこへ偵察に出ていた次郎が戻ってくる。 三郎と次郎は予てより各地の様子を探りに行っているという弁慶の説明に、義経が備えを怠りなくしていると知る吉次。 義経に西国の様子を尋ねられた次郎は、範頼の軍勢は筑前を目指しているが手前の安芸で身動きができない有様で、そのあたりは西国の平家の水軍だらけで山陽道も押さえられ、兵糧も断たれていると報告する。 そのような状況なのに、何故頼朝は義経に出陣を命じないのかと憤る三郎。 吉次は義経に、もし義経が源氏の大将ならどうするか尋ねる。 義経は、自分なら屋島の平家本陣を攻めると答える。 水軍も無い状態でと問う継信に、四国へ渡る船さえあれば良いと告げる義経。 苦悩する頼朝は、盛長(草見潤平)に自分は北条を蔑ろにしているかと尋ねる。 盛長は否定し、新しい政を目指す自分の理が物の見方を狭くしているのではと告げる頼朝を、疲れているのだと労わる。 意を決した頼朝は、御家人達に屋島の平家を討つことを法皇に願い出ると告げる。 大将を尋ねられた頼朝は、「大将は九郎判官義経」と言い放つ。 頼朝が「判官」と言ったのは義経に対する恩情かと問う時政に、「温情にあらず。試練を与えるのだ」と答える頼朝。 御所に召された義経は、「平家追討の大将に九郎判官を」と頼朝が願い出たと知康から聞かされる。 頼朝が「判官に」と書状に書いていたと聞き、義経は感激して言葉を失う。 法皇からの平家追討の大将にという命を、喜んで受ける義経。 頼朝の勘気を被っていた義経であったが、ついに平家追討の大役が仰せ付けられたのだった。 |
| 2005年8月7日放送 第三十一回「飛べ屋島へ」 後白河法皇(平幹二朗)の御所に召された義経(滝沢秀明)は、頼朝(中井貴一)の推挙により平家追討の総大将を命じられた。 帰館した義経は、弁慶(松平健)達郎党にそのことを告げ、無駄な時を過ごさせたことを心苦しく思っていたと話す。 弁慶達は義経が大将に命じられたことを喜び、改めて義経に主従することを誓う。 そこへ、頼朝から軍目付を命じられた景時(中尾彬)と景季(小栗旬)が訪れる。 義経は景時が軍目付なら心強いと告げ、景季は義経主従と共に戦に赴くことを喜ぶ。 義経は静(石原さとみ)に、今回の頼朝の恩情に応えるためにも命を投げ打つと戦に赴く覚悟を語る。 義経出陣の朝、見送る萌(尾野真千子)に義経は、万一の時は萌の好きなようにするよう告げる。 義経主従は、門番の兵に取り押さえられる鷲尾三郎(長谷川朝晴)とまごめ(高野志穂)に気付く。 自分に会いに来たのかと問う三郎(南原清隆)に、「違う」と強く否定するまごめ。 義経は訪れた鷲尾兄妹を歓迎する。 都に来た目的を聞かれたまごめは、鷲尾三郎は一ノ谷で義経の戦ぶりを見ていらい自分の猟が物足りなくなった、兄を義経の家来に加えて欲しいと願い出る。 平伏する2人に戸惑う弁慶。 継信(宮内敦士)の「もし家来になれなかったら?」との問いに、兄はただボンヤリと日を送り飢え死にすると答えるまごめ。 義経は一ノ谷で恩を受けた者を死なせては末代まで恩知らずの誹りを受けると、鷲尾三郎の郎党入りを許す。 しかし、三郎が「わしは伊勢三郎、こやつは鷲尾三郎、三郎が2人いては甚だ困る」と異を唱える。 これに対して、鷲尾三郎は幼少の頃「熊」と呼ばれていたと答え、鷲尾三郎は「熊」と名乗ることで三郎も了承する。 ついにこの日、義経は屋島の平家を追討する源氏の大将として都を発った。 丹後局(夏木マリ)から、義経が出陣したという報告を受ける法皇。 義経が取り返した三種の神器を頼朝に差し出さないか不安になる法皇に、義経はことのほか法皇を重んじているから大丈夫と答える丹後局。 讃岐・屋島。 屋島の平家にも、義経が兵を率いて出陣したことが伝わっていた。 船戦に慣れない源氏の者達が攻めてきても恐れることはないと言う宗盛(鶴見辰吾)だが、知盛(阿部寛)は西国の源氏の兵が勢いをつけ、屋島が東と西の挟み撃ちになることを憂う。 知盛は宗盛に、急ぎ長門へ向かい源氏勢を抑えると願い出る。 時忠(大橋吾郎)から義経が屋島を攻めると聞いた領子(かとうかずこ)は、ここ2、3日の能子(後藤真希)の様子が違うと時忠に告げる。 屋島の平家に従っている能子は、この2、3日、気がふさいでいた。 時子(松坂慶子)の前で、義経が屋島を攻めると聞いて何か企んでいるのではと能子を問い詰める領子。 能子は義経が屋島を攻めるとは知らなかったと答えるが、領子は何故このところ気がふさいでいたのかと問い質す。 母の常盤(稲森いずみ)が亡くなったとの報せを受けたからと答える能子。 常盤が死去したことを聞いた時子は、能子を身籠っていた常盤と会った時のことを思い出す。 摂津・渡辺。 この日、義経の軍勢は、瀬戸内を挟んで屋島の対岸にある摂津国の渡辺に到着した。 義経達を迎えた渡辺党の頭目の渡辺学(瀬野和紀)は、用意できる船は40艘だと話す。 梶原水軍と併せると150艘になるが、梶原水軍が到着するのは6、7日後だという。 景季は取り敢えず40艘で屋島へ向かうことを提案するが、義経は平家に味方する阿波の水軍や、背後に熊野水軍がいるため無理だと答える。 景時は梶原水軍が到着するまで待つことを進言するが、義経は何か他に屋島へ向かう方策を探すと話す。 その夜、三郎、次郎(うじきつよし)、喜三太(伊藤淳史)、熊は義経の命を受け偵察に向かう。 義経は偵察から戻った三郎達から、絵図を囲んで報告を受ける。 平家は船を隠して近付く義経軍を待っている筈で、見つからずに屋島に近付くには回り込んで阿波に上陸する方法がある。 しかし阿波から屋島へ向かう途中に高い山がある上、平家に味方する武者達がいる。 その上、摂津から屋島へは1日で渡れるが、阿波へは3日はかかるし鳴門の渦という難所もある。 次郎は万が一の時には、難所も乗り切れる船乗りらに声をかけると話し、義経も頷く。 1人瞑目し戦略を考えた義経は、軍議で渡辺党の40艘で阿波を目指すと告げる。 景時は、阿波から屋島へ向かう間には近藤親家、桜庭介良遠など平家に従う者がいる、それらを打ち破っても大きく立ちはだかる山並みがある、あと3、4日後に到着する梶原水軍と共に出立すべきと異を唱える。 義経は、船戦に不慣れな源氏が平家に勝つ為にはこの手立てしかないと告げ、弁慶も近藤親家の親は鹿ケ谷の密議で斬首された西光法師、親家の胸には平家への恨みもある筈と話す。 景季も義経の意見に同意し、景時もやむなく同意する。 ところが、義経が阿波へ向かおうとしたその日、摂津には春の嵐が襲いかかり、渡辺党の船40艘の多くが痛手を被った。 急いで船の修理を行うが、学によれば1、2日はかかるという。 景時は義経に梶原水軍が到着するまで待つよう進言するが、義経は梶原水軍もこの嵐で到着が遅れるのではと言う。 景時は義経に、船に逆櫓を取り付けることを進言する。 逆櫓とは舳先に備える櫓のことで、逆櫓があれば敵の船に襲われても駆け引きが容易く、退却も素早くできた。 取り付けの日数を問われた学は、逆櫓を全ての船に備えるには5日かかると答える。 義経は「待てぬ」と言い、武士が戦に向かう時に退くことを考えてはならない、いつでも逃げれると思えば兵に油断が生じると話す。 景時は、大軍を率いる将はいざという時のことを考えなければならないと告げる。 その言葉に弁慶が異を唱え、三郎や次郎もその場に駆けつける。 「次の戦に備えて味方の損傷を防ぐことも戦には肝心」と言う景時に、頼朝の恩情に応える為にはこの戦に勝ち、三種の神器を取り返さなければならない、その機会が度々あるとは考えていない、この地を発てば再び生きて帰るとは思っていない、自分達は放った矢と同じで的を外すことなく敵に向かうのみと言い放つ義経。 「それでは退くことを知らぬ猪と同じでござる」と言う景時に、弁慶は言葉が過ぎると食って掛かり、あわや掴み合いという険悪な状態を景季や継信達が制止する。 この軍勢は義経の軍勢ではなく頼朝の軍勢だと主張する景時に、大将を任された以上自分の軍勢だと主張する義経。 景時は「たとえ大将とはいえ、軍目付に計りもせずに何事も己1人のみでお決めになるとは如何なものか。これでは某、軍目付としての務めが果たせませぬ」と告げ、義経と景時は睨み合う。 雨が降り始め、自分の中では次の戦というものはない、これが最後だといつも胸に刻んで臨んでいるという義経の言葉に、景時はその場を立ち去る。 自分の陣に戻った景時は、今までの義経の戦ぶりを景季に尋ねる。 これまでの兵法を超え、臨機応変な戦ぶりと答える景季に、多くの兵を抱える大将としては兵の命も大事、仮に自分達が討死すれば梶原の所領はどうなるのか、所領も武士の命綱、義経は所領を持たないからあのように躊躇いも無いと話す景時。 義経は継信に、自分は郎党達を窮地に追いやろうとしている、けれど今の自分にはこの手立てしかないと話す。 継信は迷わず義経のしたいようにするようにと告げる。 自分が忠信(海東健)と共に奥州から義経に従ってきたのは、義経の気性を慕っているから、自分達は義経に命を捧げている、義経の思いは自分達の思いと話す継信。 義経は継信に「ついてきてくれるか」と問い、継信は「無論にござる」と答える。 風が強くなったという弁慶の報告を受けた義経は、1人で荒れる海を見つめ決断する。 義経は景時に、今夜阿波に向けて船を出すと告げる。 敵の目を晦まし見張りを欺く好機と話す義経に、反対する景時。 船はどうするのかという問いに、義経はすぐにでも出せる船が5、6艘あると答える。 景時は軍目付として承服できないが、それでもと言うなら義経の勝手と告げる。 景季は景時に、義経に従いたいと願い出る。 義経は景時に「屋島にて待つ」と告げ、景季と共に船へと向かう。 学は義経に、船の乗り手を募ったが、この先風も強くなり雨も降る時化た海に出たいという者は1人もいないと話す。 そこへ、次郎が嵐の中でも大丈夫という船乗りを4人連れて現れる。 義経は次郎を褒め、学に船を4艘借りると頼むが、次郎は元船乗りの自分も入れて5艘だと告げる。 雨風が更に強さを増したその夜、義経は150騎の兵を船5艘に分け、嵐の海に押し出した。 義経主従にとっては、この夜すでに戦が始まっていた。 |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()