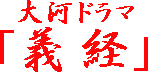
ストーリー
| 2005年10月9日放送 第四十回「血の涙」 鎌倉入りを許されない義経(滝沢秀明)は、腰越にて頼朝(中井貴一)への書状をしたため、目通りの許しを切に願い出た。 書状はこの後、満福寺の者の手によって公文所別当の大江広元(松尾貴史)へと届けられた。 公文所を通さず直接頼朝に届ければ良いのにと言う三郎(南原清隆)に、できるものならそうする、手順を踏まなければと諭す弁慶(松平健)と忠信(海東健)。 義経は広元の執り成しを待とうと告げる。 広元は義経からの書状に驚き、書状を読まずに政子(財前直見)に届けて指示を仰ぐ。 政子は広元に、頼朝には渡さず広元が読むように告げる。 書状を届けてから2日が経ったが、そのような成り行きを知らない義経は、頼朝からの返事を心待ちしていた。 そこへ千鳥(中島知子)が食べ物を持って現れる。 魚の商いで鎌倉へ行くことがあるという千鳥に、弁慶は行く時は一緒に連れて行ってほしいと頼む。 頼朝を中心にして、政子、時政(小林稔侍)、義時(木村昇)、広元、善信(五代高之)が義経の処遇について話し合っていた。 無断で賜った官位を未だに返上しない義経を鎌倉に入れるわけにはいかないと言う時政に、広元は法皇(平幹二朗)に対して角が立つのではと告げる。 政子は兄弟が会うことに障りは無いと義経と会うことを頼朝に勧めるが、頼朝は兄弟であるということは関係ないと答える。 政子は広元に義経からの書状について尋ね、広元は義経から頼朝への執り成しを願う書状がきたと頼朝に報告する。 政子に書状を読むのかと問われた頼朝は、「読むには及ばず」と答える。 ほくそ笑む政子。 政子はこれで頼朝が書状を読むことも義経と会うこともない、頼朝に義経を会わせてはならない、会えば頼朝が情に絆される恐れがある、頼朝は元々身内の情を求めているがそれを抑えて生きてきた、その縛りを解き放ってはいけないと時政と義時に話す。 義経を入れると鎌倉が乱れると言う政子に意味を尋ねる義時に、平家追討時に見事な働きをした義経に信望を寄せる武将もいる、それでは鎌倉が2つに割れると答える時政。 政子はもっと怖ろしいのは義経と頼朝が手を携えること、武士の棟梁としての頼朝の器量と軍神の如き義経の強さが1つになれば強固なる源氏の国ができる、鎌倉の為、北条家の為にも源氏に大きな力を持たせてはならないと告げる。 弁慶は義経に、商いで鎌倉に行く千鳥に付いて行き、鎌倉の様子を見たいと申し出る。 義経は弁慶に「待とう」と告げ、弁慶も頷く。 京。 知康(草刈正雄)から、義経が鎌倉に入れてもらえず腰越で留められているという報告を受ける法皇。 頼朝は法皇の使いである義経を拒絶するという、法皇を恐れぬ振る舞いをしたと告げる丹後局(夏木マリ)。 法皇は頼朝が都にいて顔色が窺えれば打つ手もあるが、それができないのがもどかしいと嘆く。 頼朝の前に現れた広元は、宗盛(鶴見辰吾)と清宗(渡邉邦門)の処遇について尋ね、このまま鎌倉にいても役に立たないので都に返すことを進言する。 頼朝は2人の処分を法皇に任せるのも見物だが、急ぐことはないと答える。 義経からの書状の内容を問う頼朝に、義経の書状を差し出す広元。 読むつもりはないと答える頼朝だが、広元は自分1人が抱えるには重過ぎると告げ、書状を置いて立ち去る。 鎌倉からの沙汰を待つ宗盛の前に清宗が現れ、頼朝のことを褒める。 清宗は、鎌倉には様々な役所が設けられ、頼朝は武家の為の政を都ではなく鎌倉でしようとしていると話す。 これは亡き清盛(渡哲也)が福原で目指していた国造りと同じではないかと言う清宗に、そのようなことは夢幻、幻は時として人を食い殺す、清盛もそれに食い滅ぼされたようなものと告げる宗盛。 食料調達をして戻った三郎と次郎(うじきつよし)を迎える忠信、喜三太(伊藤淳史)、義久(長谷川朝晴)。 そこへ義経と弁慶が現れ、喜三太と義久が作った籠を褒める。 このようなことをさせていることを郎党に詫びる義経に対して思わず怒る三郎と、それをからかう次郎。 2人のやりとりを見て、義経も微笑む。 弁慶は忠信が彫っている仏像に気付き、仏像の顔が亡き継信(宮内敦士)に似ていると告げる。 義経もその仏像を手に取り、「継信じゃ」と頷く。 夜、変装をした三郎、次郎、喜三太、義久の4名は、止める忠信を振り切って出かけようとする。 そこに弁慶が現れ、何をしているか問われた三郎たちは、義経の姿が痛ましい、一ノ谷や壇ノ浦で共に戦った御家人に義経への力添えを頼みに行くと答える。 しかし、弁慶は三郎たちの心中は解るが寺を出てはならない、万一騒ぎになれば義経を窮地に追い込むことになると強い口調で引き留める。 頼朝は義経の書状の入った箱の紐を解き蓋を開けようとするが、悩んだ末に書状を読むことをやめる。 籠を作るなどそれぞれ時間を過ごす弁慶たちと、雨を眺めながら頼朝からの使者を待つ義経。 三郎は義経に書状は頼朝の元に届いてないのではと言い、忠信と弁慶はのんびりと待てば良いと告げる。 広元に確かめてはと進言する三郎に、義経は催促がましいことはできないと答える。 書状は頼朝の元に届いていて、返事がないのが頼朝の返事かもしれない、自分は鎌倉には不要なのかもしれないと告げる義経。 異を唱える次郎たちに、義経は鎌倉の御家人から離れた時の覚悟を求める。 その時は主もなく暮らしを立てる所領も望めないと言う義経に、忠信はその時は平泉があると告げる。 しかし、義経は平泉には行けない、やはり秀衡(高橋英樹)の意を受けていたのかと頼朝に思われると答える。 三郎は事ここに及んでどう思われてもと反論するが、義経は頼朝に誤解だけはしてもらいたくないと話す。 弁慶は義経に異議があると言い出し、「我らに主はないと申されたことでござる。我らに主がござる。九郎義経という主が」と告げる。 次郎は良く言ったと弁慶を褒め、三郎は「たまには良いことを言う」と泣き弁慶に怒鳴られる。 明るく笑う郎党を見て、微笑む義経。 この日、御霊神社に参拝した頼朝は稲村ヶ崎へ回った。 馬の足を止めた頼朝は、供をした義時に「あの岬の辺りが腰越じゃな」と尋ね、その方向を見つめる。 夜、1人となった頼朝は、意を決して箱から書状を取り出して読む。 読み終えた頼朝は「九郎、何故そこまで情を欲する。情はならぬと申しておるこのわしに。何故わしを苦しめる」と呟き、書状を強く握りしめる。 「読まねば良かった」と涙を流す頼朝。 翌日、頼朝は時政らを前にして、義経への沙汰を下す。 「無断任官した上、未だ官位を返上せぬこと許しがたし。九郎はかねてより公私のけじめを畏れず、それは情実に縋る気風からも窺える。よって鎌倉へは入れぬ」という頼朝の言葉を聞き、満足そうに頷く政子。 鎌倉から使者が来たという喜三太の報せに、飛び出す義経主従。 そこに使者として時政が現れ、義経に宗盛と清宗を伴って都に立ち返るようにとの頼朝の命令を伝える。 驚く義経主従。 義経は頼朝との対面はと尋ねるが、時政は支度が整い次第発てとのことなので目通りは叶わないと答えて立ち去る。 その夜、1人で堂に篭った義経は、握り拳を床に激しく打ちつけながら嘆き苦しむ。 心配して外で義経が出てくるのを待つ郎党。 三郎はひょっとして義経が命を絶つのではと心配し、弁慶はただ涙を流す。 翌朝、中から出てきた義経は、「もはや立ち去るのみ」と弁慶たちに告げる。 支度を整えた次郎たちは杢助(水島涼太)に世話になった礼を言い、弁慶と千鳥は泣きながら別れる。 出立するために迎えに現れた義経に、宗盛は「我らは何のために鎌倉に参ったのであろうか」と告げる。 その宗盛の言葉は、義経と同じ思いであった。 義経主従は宗盛と清宗を連れ、腰越を出立する。 鎌倉から1人、義経を見送る頼朝。 元暦2年6月、二度と訪れることのない鎌倉であった。 |
| 2005年10月16日放送 第四十一回「兄弟絶縁」 義経(滝沢秀明)は頼朝(中井貴一)との対面も叶わず、都へ帰ることとなった。 兄・頼朝の義経への仕打ち、その真意を推し量っては打ち消し、打ち消しては思案する旅の途上であった。 義経の前に、宗盛(鶴見辰吾)と清宗(渡邉邦門)が現れる。 宗盛は義経に自分たちの処分について尋ね、弁慶(松平健)は都へ戻った後に然るべき沙汰が下されるのではと答える。 宗盛は鎌倉を出てからの義経の顔色が険しい、何か重いものを抱えているのではと問うが、義経は何もないと答える。 鎌倉。 思案する頼朝の前に現れた政子(財前直見)は、義経に対する処置を悔やむことはないと告げる。 頼朝は思案は義経への沙汰ではないと答え、その場を立ち去る。 別の場所にいた頼朝の前に、時政(小林稔侍)と広元(松尾貴史)が現れる。 時政は義経の恨みが頼朝への謀反の心を芽生えさせるのではないかと告げ、頼朝も自分の胸につかえているのはそのことだと答える。 宗盛と義経が万が一組むことになれば、各地に散り散りになっている平家の武士が集まって侮れない力となる、義経の力を削がなければならないと話す頼朝。 時政と広元は、義経に与えた元平家の領地24箇所を取り上げること、清盛(渡哲也)が頼朝と義経に情けをかけて滅んだという轍を踏んではならないと進言する。 喜三太(伊藤淳史)と義久(長谷川朝晴)から、近くの寺に重衡(細川茂樹)が先頃留まっていたという報告を受けた義経は、宗盛と清宗にそのことを知らせる。 義経は平家の人々は兄弟仲睦ましく見えると告げるが、宗盛はそれは一門がこのような有様になったからと答える。 兄の重盛(勝村政信)を敬うよりも怖れ、弟の知盛(阿部寛)の強さに僻み、弟の重衡の真っ直ぐさが眩しかった、自分は心が狭過ぎたと話す宗盛。 重衡は南都ではなく、山城国・木津にいた。 鎌倉の使者から、僧兵らに身柄を引き渡される重衡。 重衡の妻の輔子(戸田菜穂)は、重衡が南都に入ったと聞き、一目会うために寺を訪ねていた。 僧侶から南都焼討について問われた重衡は、全て自分の所業、いかなる罰も受け入れる覚悟と答える。 翌日、重衡は処刑されることとなった。 寺の境内で重衡が覚悟を決めたその時、重衡の名を呼ぶ声が聞こえる。 声の主が輔子と気付いた重衡は、僧侶に輔子との今生の別れを願い出、僧侶はそれを許す。 重衡と対面を果たした輔子は、泣きながら重衡に「形見を」と申し出る。 重衡は自分の髪を噛み切って形見として輔子に手渡し、「決して私の後を追うてはならぬ。生きよ、寿命尽きるまで生きよ。さすれば、来世にて巡り会うこともあろう」と告げる。 輔子が僧兵によって寺の外へ出された後、重衡は斬首される。 三位中将重衡は、29歳でその命を終えた。 法皇(平幹二朗)は、清盛の子で生きているのは宗盛だけになったと告げる。 宗盛が都に戻った時は、自分たちのために使うことができるかという丹後局(夏木マリ)の問いに、宗盛より義経と答える法皇。 義経が都に戻るのが待ち遠しいという丹後局の言葉に、笑う法皇と知康(草刈正雄)。 義経一行は、近江国・篠原にまで旅を進めていた。 明日には都入りとなり、宗盛は義経に途上で首を刎ねられるものと思っていたが、都に戻ったら仏門に入って亡くなった一門の弔いをしたいと話す。 そこへ忠信(海東健)が現れ、鎌倉からの使者が到着したと報せる。 鎌倉の使者として訪れた盛長(草見潤平)は、宗盛と清宗の首を刎ねるよう告げる。 驚く義経は宗盛に謀反の恐れはないと反対するが、盛長は自分は頼朝の言葉を伝えに来たのみと告げ義経に返答を求める。 都に戻ってからと答える義経に、盛長はこの地での処刑を求め、自分は宗盛の死を検分してから鎌倉に戻ると告げる。 盛長に返答を迫られた義経は、宗盛と清宗の処刑を受け入れる。 宗盛は義経と昔話をしたいと申し出、義経もそれに応じる。 2人きりになった義経と宗盛は、義経が牛若と呼ばれていた頃の話をする。 宗盛は牛若を妬んでいたと告げ、父に対する思いや福原が描かれた屏風の話をする。 義経は清盛が語った新しき国について話し、宗盛は義経の中に清盛の思いがあったことを知る。 宗盛は自分たちはこの地で討たれるのかと義経に尋ねる。 答えに困る義経に、平伏して清宗の命請いを願い出る宗盛。 そこに清宗が現れ、そのような申し出は義経を困らせるだけ、清盛に助けられたために今日があることを身に染みている頼朝が、それを許す筈はないと告げ、宗盛も納得する。 そして翌日、清宗が処刑された後、盛長や義経主従の目の前で宗盛は処刑される。 宗盛は懐かしい都を目前にして、39歳の生涯を閉じた。 これにより平家は潰えた。 翌朝、弁慶たちの前に現れた義経は、宗盛斬首は平家の血筋を絶やすという目的以外に、宗盛を討てるか頼朝が自分を試していた、つまり自分に不審を抱いていた、頼朝がそのようなつもりならば頼朝に付き従う思いも気力も失せた、この後自分は頼朝とは別の道を歩むと決めた、自分なりの新しき国を探しだそうと思うと告げる。 三郎(南原清隆)は「我ら、付き従いまする」と力強く答え、義経はこのような思いが鎌倉に伝われば、頼朝との間に抜き差しならない思いも生まれると郎党に覚悟を求める。 弁慶、忠信、三郎、次郎(うじきつよし)、喜三太、義久は何があっても義経に付き従うのみ、自分たちはいつでも義経の側にいると告げる。 弁慶たちの思いを受け止めた義経は、弁慶たちと共に都へと出立する。 義経はついに、求めても求めても受け入れてはくれない頼朝の懐から飛び出す決意をした。 そして、この日から義経主従には苦難の日々が待ち受けていた。 |
![]() (一部敬称略)
(一部敬称略)
このページTOPへ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()